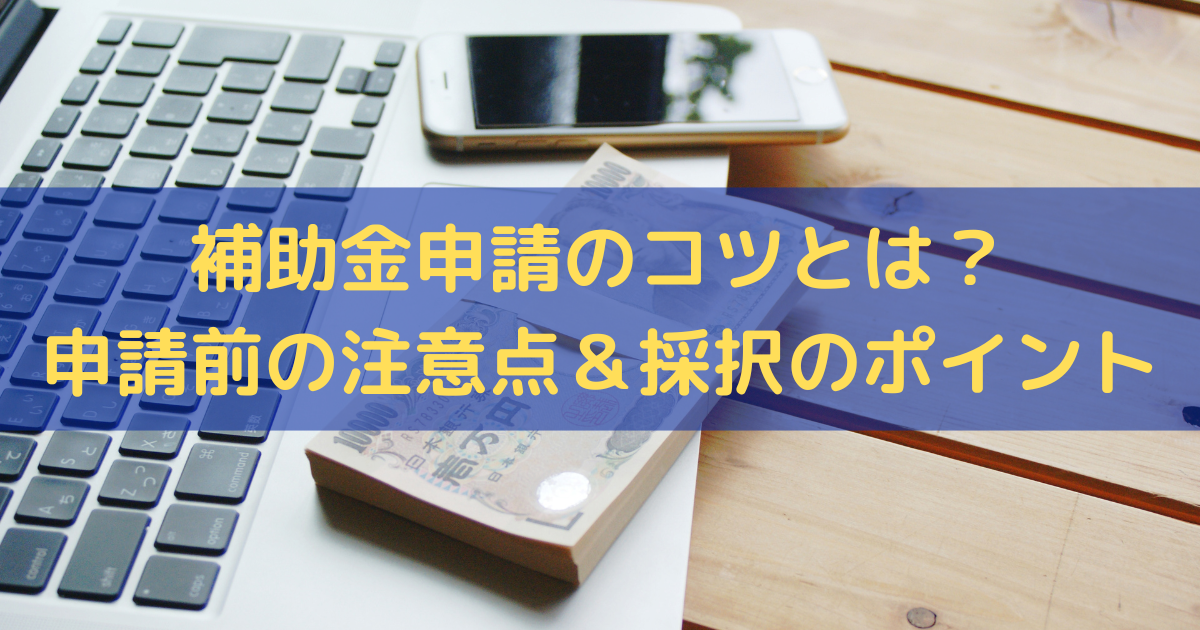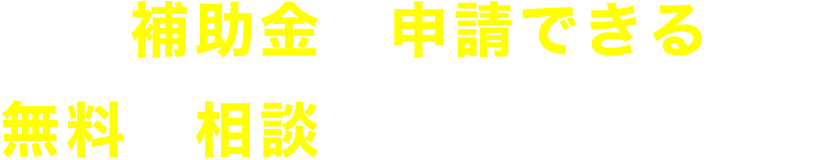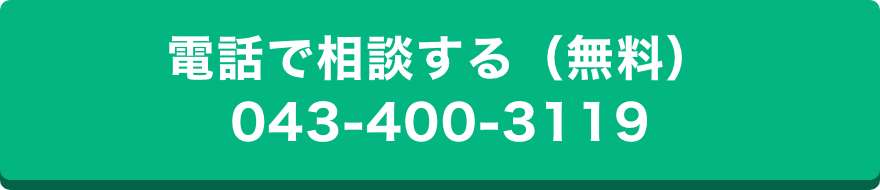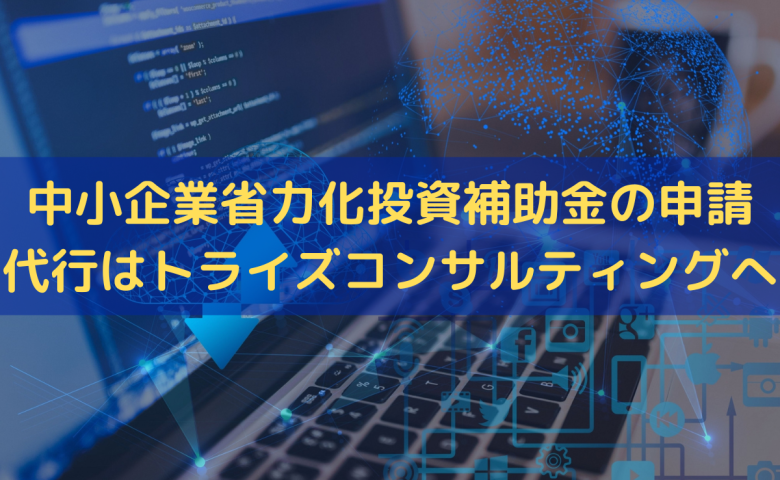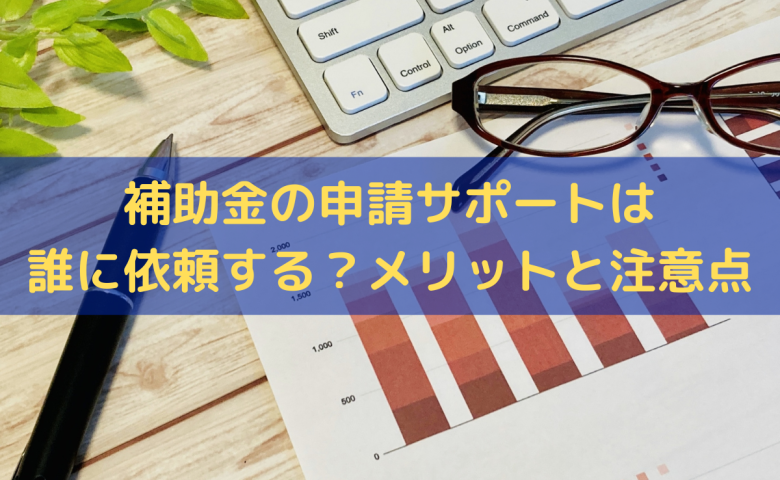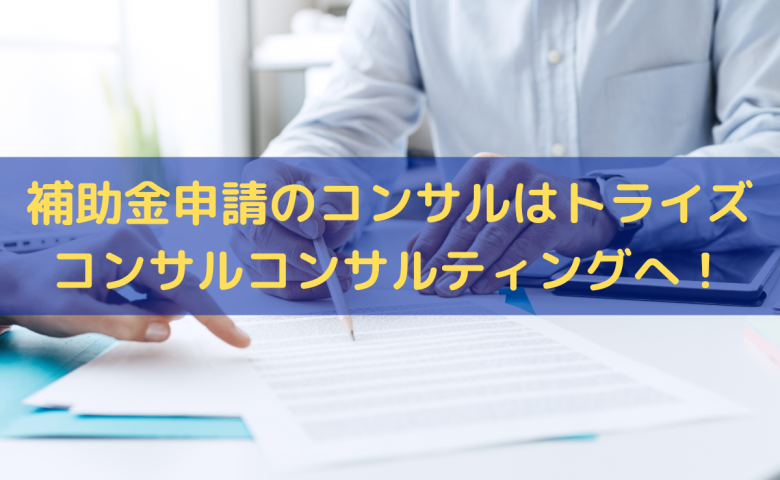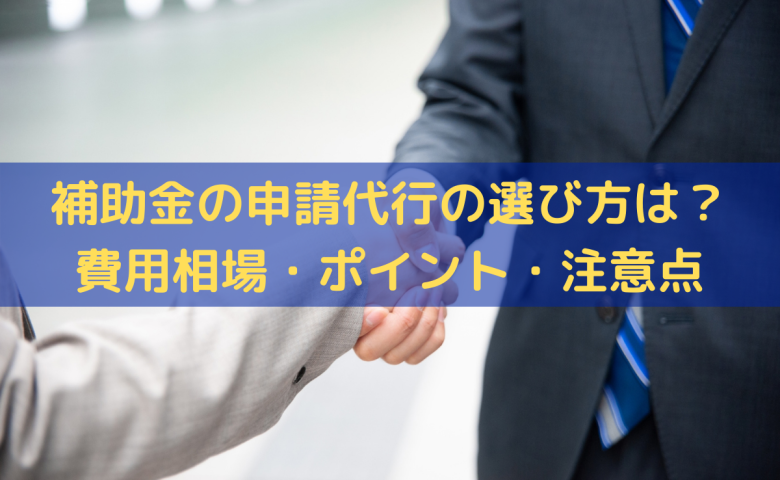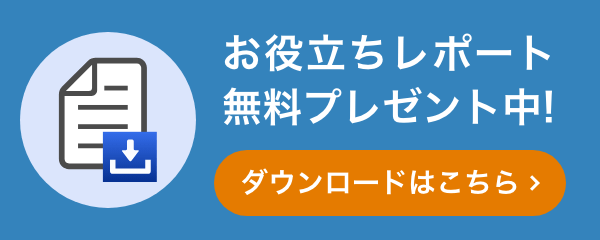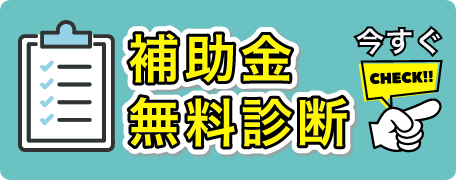補助金とは、所定の申請要件を満たして公募期間内に申請することで、国や地方公共団体などからまとまった事業資金を受け取れる制度です。融資とは異なり、不正受給などの場合を除き、原則として返済は必要ありません。補助金を上手に活用することで思い切った事業投資が可能となり、事業の成長スピードを格段に早めることにつながるでしょう。
ただし、補助金は申請したからといって必ず受け取れるものではありません。補助金を受給するには最低限の申請要件を満たしたうえで、多数の申請の中から「その補助金の交付対象に相応しい」として選ばれる必要があります。これを、「採択」といいます。特に大型の補助金で採択を勝ち取るハードルは高く、採択を受けるには補助金申請のコツを熟知した専門家のサポートを受けることが近道といえるでしょう。
では、補助金に採択されるための申請のコツには、どのようなものがあるのでしょうか?また、補助金に採択されるためには、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?今回は、補助金に採択されるための申請のコツや注意点などを解説するとともに、2025年6月時点における主要な補助金の最新情報を紹介します。
なお、当社トライズコンサルティングは補助金のサポート実績が豊富であり、補助金に採択される申請のコツを熟知しています。トライズコンサルティングは、中小企業診断士の野竿が代表を務めるコンサルティング会社です。コツを踏まえた補助金申請をご希望の際や自社に合った補助金が知りたい際などには、トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。
補助金と助成金の違い
補助金と似たものに、「助成金」があります。
厳密には補助金と助成金を明確に区分することはできないものの、厚生労働省管轄の助成金に限れば、補助金との違いを整理することが可能です。
初めに、補助金と助成金の共通点や主な違いについて解説します。
補助金と助成金の共通点
補助金と助成金はいずれも、国などから返済不要な資金を得られる制度です。
ただし、いずれも不正受給などが発覚した場合は、例外的に返還が求められます。
補助金は事業計画の策定が必要である
補助金を申請するには、原則として事業計画の策定が必要となります。
これは、多くの補助金が事業の成長、ひいては税収の増加や日本経済の底上げなどを目的として設けられているものであるためです。
一方、助成金は申請の要件を満たすことを示す申請書の作成のみで申請することが可能であり、事業計画の策定までは求められないことがほとんどです。
補助金は採択されないと受け取れない
補助金は、要件を満たして申請したからといって必ずしも受け取れるものではありません。
補助金を受け取るためには、要件を満たして期限内に申請したうえで、多数の申請の中から採択されることが必要です。
一方で、助成金には「採択」という概念がなく、所定の要件を満たして申請することで受け取れるものがほとんどです。
補助金は原則として後払いである
補助金は、採択されたからといってすぐに振り込まれるものではありません。
補助金は原則として後払いであり、採択後にはまず自社で補助対象とした事業の実施(費用の支出など)をして、実際にかかった経費の精算として交付されます。
一方、助成金は申請要件に合致してさえいれば事務局によって手続きがなされ、一定期間後に支給されることが一般的です。
補助金を申請するメリット
企業が補助金を申請することには、どのようなメリットが考えられるでしょうか?ここでは、主なメリットを3つ解説します。
- 返済不要の資金を調達できる
- 自社の事業の見直しができる
- 対外的に信用が高まる
返済不要の資金を調達できる
1つ目にして最大のメリットは、返済不要なまとまった資金を得られることです。
補助金は不正受給などをしない限り、原則として返還する必要がありません。また、ファンドからの出資受け入れなどとは異なり、株式を差し出す必要もありません。
企業にとって返済不要なまとまった資金を得られる機会は稀であり、貴重な投資資金となるでしょう。返済不要なまとまった資金を得ることで思い切った投資が可能となり、事業の成長スピードを早めることへとつながります。
自社の事業の見直しができる
2つ目は、自社の事業を見直すきっかけとなることです。
多くの補助金で、申請にあたって事業計画書の提出が求められています。この事業計画書の練り込みが、採択されるかどうかを左右するといっても過言ではありません。
そのため、補助金を申請するにあたっては自ずと自社の事業計画と真剣に向き合う必要が生じ、事業計画を見直すきっかけとなります。
対外的に信用が高まる
3つ目は、補助金の採択を受けることで、対外的な信用が向上しやすいことです。
事業再構築補助金やものづくり補助金など大型の補助金では、採択された事業者名や事業の概要などが補助金の公式ホームページで公表されます。これら大型の補助金で採択を勝ち取ることは容易ではなく、さまざまな角度から事業計画を検討し、実現性の高い計画を策定しなければなりません。
このような過程を経て採択を勝ち取ったという事実は、事業計画がある程度信頼できるものであるとの印象となり、金融機関など外部からの信用が向上する効果が期待できます。
補助金を申請するデメリット
補助金を申請することには、何らかのデメリットはあるのでしょうか?
ここでは、主なデメリットを4つ解説します。
- 申請手続きに手間がかかる
- 必ずしも採択されるとは限らない
- 不要な投資に繋がるリスクがある
- 採択後の手続きに手間がかかる
申請手続きに手間がかかる
補助金は、申請手続きに手間がかかります。
特に大型の補助金を自社のみで申請しようとすれば、本業に割くべきリソースを圧迫してしまう事態となりかねません。
そのため、専門家による申請サポートを受けることをおすすめします。
必ずしも採択されるとは限らない
先ほども解説したとおり、補助金は要件を満たして申請したからといって、必ずしも受け取れるものではありません。
時間や労力を投じて申請しても不採択となってしまえば、補助金は支給されないということです。
不要な投資につながるリスクがある
補助金を申請する際は、補助金を使って行う投資が「たとえ補助金がなくても行いたい投資なのか」を十分に検討することをおすすめします。
なぜなら、補助金がもらえるということで財布の紐がゆるんでしまい、不要な投資や過剰な投資をしてしまうおそれがあるためです。
補助金を活用した結果、資金繰りに窮することとなれば本末転倒です。
なお、補助金でかかった経費の全額が補填されることは稀であり、多くは経費の「2分の1」や「3分の1」など一定割合が補助率とされています。
採択後の手続きに手間がかかる
補助金は、採択後の手続きにも相当の手間がかかります。
多くの補助金で、採択後にはまず「交付申請」が必要です。
その後、事業を実施した後は、これについて「実績報告」もしなければなりません。
特に大型の補助金ではこれらの手続きにかかる手間も大きく、なかには手続きの負担からせっかく採択された補助金の受給を諦めるケースもあるほどです。
このような事態を避けるため、補助金の申請サポートを専門家へ依頼する際は、採択後の手続きについてもサポートしてくれる専門家を選ぶことをおすすめします。
交付申請
実績報告
補助金を申請する前の注意点
補助金を申請する際は、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?
主な注意点を、3つ解説します。
- 取り組みが制度の趣旨に合致しているか
- 応募期限や採択率に無理がないか
- 投資資金は準備できるか
取り組みが制度の趣旨に合致しているか
補助金にはそれぞれ、補助金制度を設けている趣旨や目的があります。
この趣旨や目的からズレていると、いくら社会的意義のある事業であっても採択を受けることは困難です。
そのため、補助金を申請する際はその補助金の趣旨を読み込み、補助金を使って行おうとする取り組みがこの趣旨に沿っているかあらかじめご確認ください。
応募期限に無理がないか
補助金はいつでも申請できるものではなく、公募期限が設けられています。
補助金を申請する際は公募期限が間近に迫ってから準備に取り掛かるのではなく、期限に余裕を持って準備を進めるようにしてください。
なぜなら、期限ギリギリになってから申請準備を始めると申請書類が急ごしらえとなりやすく、見直しに必要な時間も確保しづらくなるためです。
このような申請では、採択が遠のいてしまうでしょう。
また、期限間近となると専門家のスケジュールが埋まってしまい、希望する専門家にサポートを依頼できない可能性も高くなります。
投資資金は準備できるか
補助金は事業資金を100%補填してくれるものではなく、経費の2分の1や3分の1など一定割合を補助してくれるものです。
また、補助金は事業実施後の後払いであるため、事業を実施するタイミングでは補助金はまだ手元にありません。
そのため、補助対象とする事業を実施するには、経費の全額をいったん自社で用意することが必要です。
この資金が用意できなければ補助対象事業が実施できず、たとえ補助金に採択されても絵に描いた餅となりかねません。
このような事態を避けるため、補助金を活用する際は資金を用意する方法についても併せて検討しておいてください。
大型の補助金では、融資を併用することが一般的です。
補助金を申請する際のコツ
補助金の採択を受けるための申請のコツは、どのような点にあるのでしょうか?ここでは、補助金を申請するコツを5つ解説します。
- 補助金の情報を幅広く収集する
- 制度の趣旨に沿った内容を記載する
- 申請書はわかりやすく作成する
- 添付資料の不足・漏れに注意する
- 採択されるまでが申請だと考える
補助金の情報を幅広く収集する
補助金は、非常に多く存在します。国などが公募するもののほか、都道府県や市区町村が設けているものも少なくないためです。そのため、自社に合った補助金を見つけるためには、幅広い情報収集がポイントとなります。
たとえば、次のウェブサイトでは補助金の情報が広く掲載されており、参考となります。
とはいえ、膨大な補助金情報がヒットすることもあり、その中から自社に合った補助金を見つけることは容易ではありません。そのため、無理に自社で探すのではなく、当社トライズコンサルティングなど補助金の専門家に相談してみることも一つの手です。
制度の趣旨に沿った内容を記載する
補助金にはそれぞれ、その補助金制度を設けている政策的な目的があります。補助金の申請書類を作成する際は、その補助金の目的をよく理解したうえで作成してください。
その補助金の趣旨目的を理解したうえで、その内容に沿っていることを申請書類の中で説明することで、採択を勝ち取りやすくなります。
申請書はわかりやすく作成する
補助金の審査をする審査員は、自社が属する業界のプロではありません。そのため、その業界にいない人であってもわかるよう、わかりやすく作成することが採択を得るためのコツとなります。
たとえば、専門用語を記載する際は、用語の意味を記載するとよいでしょう。また、「その業界では常識であるものの、社会一般の常識とはいえない内容」がある場合は業界の常識などの前提条件をしっかりと記載することで、より伝わりやすい申請書類となります。
添付資料の不足・漏れに注意する
補助金にはそれぞれ、申請時に添付すべき書類が定められています。また、申請する枠によって、必要書類が別途指定されていることも少なくありません。
補助金を申請する際は、添付書類に不足や漏れがないよう十分確認したうえで申請してください。なぜなら、必要な書類に不足があるからといって補助金事務局から種類の追完を求めてくれることはほとんどなく、多くはそのまま不採択となってしまうためです。
採択されるまでが申請だと考える
補助金に一度不採択となったからといって、諦める必要はありません。事業計画をブラッシュアップしたうえで再度申請にチャレンジすることで、次回は採択される可能性があるためです。
補助金は不採択となった場合はその時点で諦めるのではなく、不採択がわかったら、その時点から次回の公募へ向けて申請書類を見直すことをおすすめします。また、自社で申請して不採択となった場合は、次回の申請にあたって専門家によるサポートを受けることも一つの手です。
申請書類を作成する際の注意点・書き方のポイント
せっかく補助金を申請するのであれば、やはり採択を勝ち取りたいことでしょう。では、補助金の採択を受けるため、申請書類の作成に際してどのような注意をすれば良いのでしょうか?主な注意点と書き方のコツは、次のとおりです。
- 書き始める前に申請内容をよく練り込む
- 審査項目を踏まえて作成する
- 第三者から見てわかりすい内容を心がける
- 全体の整合性を確認する
書き始める前に申請内容をよく練り込む
補助金の申請書類をいきなり書き始めることはおすすめできません。書き始める前に、まずは申請内容をじっくりと練り込むことが必要です。
特に、ものづくり補助金や事業再構築補助金など大型の補助金では補助上限額が大きく、多くの事業者が採択へ向けてしのぎを削っています。そのような中で、検討の甘い申請書類を出したとしても採択を受けるのは困難でしょう。
そのため、まずは申請内容をしっかりと練り込むことが必要です。しかし、この作業を自社のみで行うことは、容易ではありません。
そこで、コンサルタントへ補助金の申請サポートを依頼して申請内容のコンサルティングを受けると良いでしょう。
審査項目を踏まえて作成する
申請内容を十分に練り込んだら、これを申請書類に落とし込みます。この際には、その補助金の審査項目を踏まえて記載しましょう。
補助金にはそれぞれ審査で重視される項目があり、ものづくり補助金や事業再構築補助金ではこの審査項目が公募要領で公開されています。そのため、まずはこの審査項目をしっかりと読み込んで理解をしたうえで、この審査項目をアピールするのに効果的な内容で記載してください。
なお、専門家に申請サポートを依頼した場合には、専門家側でこの審査項目に沿った申請書類を作成してくれることが一般的です。
第三者から見てわかりすい内容を心がける
補助金の審査員は、その業界に熟知しているわけではありません。そのため、申請書類を作成する際には、業界に精通していない第三者にとっても理解しやすい内容で作成することが必要です。
まず、業界内では知られていても一般の人にとって馴染みの薄い用語には、解説をつけると良いでしょう。
また、たとえ業界内では画期的な取り組みであったとしても、外部から見ればその素晴らしさが十分に理解できないかもしれません。そのため、業界の事情や背景などについても、申請書類の中で丁寧に説明することをおすすめします。
全体の整合性を確認する
補助金の申請書類を一通り作成した後は、申請書類を数回見返し、全体の整合性を確認することをおすすめします。なぜなら、細部を修正していくうちに、他の項目と矛盾が生じている可能性があるためです。
大きな矛盾があれば、審査員から補助事業の実現性に疑問を持たれ、採択が遠のいてしまうかもしれません。自分で矛盾点に気付くことが難しい場合には、外部の専門家などに申請書類のチェックを依頼することも一つの手でしょう。
補助金が採択されるために押さえたいポイント
せっかく手間や時間をかけて補助金に申請する以上、採択を得たいことかと思います。は、補助金に採択されるためにはどのようなポイントを踏まえればよいのでしょうか?
ここでは、補助金の採択を勝ち取るためのコツを4つ解説します。
- 加点項目を押さえる
- 事業計画を見直す
- 他の補助金に申請する
- 専門家にサポートを依頼する
加点項目を押さえる
補助金のなかには、審査において加点となる項目が設けられており、これが公表されていることがあります。しかし、せっかく加点されるための要件を満たしていても、所定の事項を申請書類に記載したり所定の書類を添付したりしない限り加点の措置が受けられないことが少なくありません。
そのため、補助金を申請する際は加点項目をあらかじめ確認し、要件を満たせそうなポイントについては漏れなく適用を受けるように注意しましょう。
事業計画を見直す
ものづくり補助金や事業再構築補助金など大型の補助金では、事業計画が採否を左右するといっても過言ではありません。そのため、さまざまな角度から事業計画を見直し、隙のない計画を策定することが重要です。
事業計画はあくまでも「計画」であり、必ずしもその計画どおりに事業が進行するとは限りません。しかし、だからといって何の根拠もなく適当に作成してしまうと、実現性が低いと判断され、採択が遠のいてしまう可能性があります。
他の補助金に申請する
補助金は採択されるまで、何度も同じ補助金に申請することが可能です。しかし、ある補助金に申請しても一向に採択がされない場合は、その補助金の趣旨目的と自社の申請内容とがズレているのかもしれません。
そのため、申請する補助金を変えてみることも1つです。申請する補助金がわからない場合は、専門家へご相談ください。
専門家にサポートを依頼する
特に大型の補助金では、自社のみで申請して採択を勝ち取ることは容易ではありません。そのため、専門家に申請サポートを依頼することが補助金獲得を成功させるポイントとなります。
専門家にサポートを依頼することで、事業計画を練り込むコンサルティングを受けることができ、事業計画の精度を高めることが可能となるためです。また、その補助金の趣旨目的や審査ポイント、加点項目などを踏まえて申請書類のサポートを受けられることからも、採択の可能性を高めることへとつながります。
2025年6月時点のおすすめの補助金
補助金制度は、非常に多く存在します。また、年度によって制度自体が新設・廃止されたり、公募内容が改訂されたりすることも珍しくありません。そのため、現在どの補助金が存在するのか、また自社はどの補助金に申請できるのかわからないことも多いでしょう。
ここでは、2025年6月時点の情報をもとに、おすすめの補助金の概要を解説します。申請のコツを踏まえた補助金申請サポートをご希望の際や自社で活用できる補助金が知りたい際には、トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。
- ものづくり補助金
- 事業再構築補助金
- IT導入補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 中小企業省力化投資補助金
- 中小企業新事業進出補助金
- 中小企業成長加速化補助金
- 大規模成長投資補助金
- 事業承継・引継ぎ補助金
ものづくり補助金
ものづくり補助金とは、中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた
新製品・新サービスの開発に必要な設備投資などを支援する補助金です。
「ものづくり補助金」と略されることが多いものの、正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。略称が浸透していることから、製造業や建設業などいわゆる「ものづくり企業」でしか活用できない補助金であるとの誤解が少なくありません。
しかし、実際は製造業などのほか、飲食業や小売業、サービス業などさまざまな業種で活用できます。
ものづくり補助金の申請枠と補助上限額は、それぞれ次のとおりです。
| 申請枠 | 従業員数 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 製品・サービス高付加価値化枠 | 5人以下 | 750万円 | ・中小企業:1/2 ・小規模・再生:2/3 |
| 6~20人 | 1,000万円 | ||
| 21人~50人 | 1,500万円 | ||
| 51人以上 | 2,500万円 | ||
| グローバル枠 | - | 3,000万円 | ・中小企業:1/2 ・小規模:2/3 |
補助下限額は、いずれも100万円に設定されています。また、大幅な賃上げに取り組む事業者は、補助上限額が100万円から1,000万円上乗せされます。さらに、最低賃金の引き上げに取り組む事業者は、補助率が2/3へと引き上げられます。
この「最低賃金の引き上げに取り組む事業者」とは、一定期間において、3か月以上にわたって「地域別最低賃金+50円以内」で雇用している従業員が全従業員数の30%以上である事業者を指します。
当社トライズコンサルティングではものづくり補助金の申請サポート実績が豊富であり、申請のコツを熟知しています。トライズコンサルティングとは、中小企業診断士が代表を務めるコンサルティング会社です。
ものづくり補助金への申請をご希望の事業者様は今後の情報に注意しつつ、トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。
事業再構築補助金
事業再構築補助金は新型コロナ禍で誕生した補助金であり、多くの事業者に活用されてきました。しかし、2025年3月26日に締め切られた第13回公募をもって廃止されており、今後申請することはできません。申請をご希望の際は、事業再構築補助金の後継に位置づけられている「中小企業新事業進出補助金」など、他の補助金の活用を検討するとよいでしょう。
なお、当社トライズコンサルティングでは採択後の交付申請や実績報告についてのサポートも可能です。事業再構築補助金に採択されたものの、採択後の手続きでお困りの際は、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。
IT導入補助金
IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。ITツールを導入する場合は、IT導入補助金の活用を検討するとよいでしょう。
IT導入補助金では補助金の受給を希望する事業者が自由に投資対象とするツールを選ぶのではなく、あらかじめ設けられたカタログの中から投資するITツールを選定することとされています。
IT導入補助金のホームページの「ITツール・IT導入支援事業者検索」から対象のITツールを検索してみると、イメージが湧きやすくなるでしょう。「ITツール」の幅は非常に広く、会計ソフトなどの業務用ソフトからPOSレジやタブレットなどまで、さまざまなツールが対象となることがわかります。
2025年度におけるIT導入補助金の今後の申請枠や補助上限額は、次のとおりです。
| 枠 | 通常枠 | インボイス枠 | 複数社連携IT導入枠 | セキュリティ対策推進枠 | ||||
| 類型 | 1プロセス以上 | 4プロセス以上 | 電子取引類型 | インボイス対応類型 | ||||
| 補助額 | 5万円~150万円 | 150万円~450万円 | 350万円 | ITツール | PC・タブレット等 | レジ・券売機等 | (1)インボイス対応型対象経費:左記同様 (2)消費動向等分析経費:50万円×グループ構成員数 (3)事務費・専門家費:200万円 ※(1)+(2)の上限は3,000万円 | 5万円~150万円 |
| ・1機能:~50万円 ・2機能以上:~350万円 | ~10万円 | ~20万円 | ||||||
| 補助率 | 1/2以内(最低賃金近傍の事業者は2/3) | ・大企業:2/3 ・中小企業:1/2 | ・~50万円:3/4(小規模事業者は4/5) ・~350万円:2/3 | 1/2 | ・(1):インボイス対応型と同様 ・(2)(3):2/3以内 | ・中小企業:1/2 ・小規模事業者:2/3 | ||
なお、「最低賃金近傍の事業者」とは、3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員数が、全従業員数の30%以上である事業者を指します。
申請をご希望の際や自社に適した申請枠がわからない場合などには、専門家へご相談ください。適切な申請枠を選択することが、IT導入補助金に申請するコツといえます。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金とは、商工会・商工会議所等と一体となって経営計画を作成し、計画に基づいて行う販路開拓などの取り組みを支援する補助金です。
チラシの印刷費や広告出稿費、ウェブサイト構築費、展示会出展費などが広く補助対象とされており、非常に使い勝手のよい補助金であるといえます。小規模事業者が新たなマーケティング活動に取り組もうとする際には、小規模事業者持続化補助金の活用を検討するとよいでしょう。
2025年における小規模事業者持続化補助金の申請枠や補助上限額は、次のとおりです。
| 申請枠 | 補助上限額 | 補助率 | |
| 一般型 | 通常枠 | 50万円 | 2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4) |
| (インボイス特例) | 通常枠に50万円上乗せ | ||
| (賃金引上げ特例) | 通常枠に150万円上乗せ | ||
| 災害支援枠 | ・直接被害:200万円 ・間接被害:100万円 | 定額、2/3 | |
| 創業型 | 200万円(インボイス特例の適用あり) | 2/3 | |
| 共同・協業型 | 5,000万円 | ・地域振興等機関:定額 ・参画事業者:2/3 | |
| ビジネスコミュニティ型 | 50万円(2以上の補助対象者が共同で行う場合は100万円) | 定額 | |
一般型通常枠や創業型では、インボイス特例の要件を満たすことで、補助上限額がさらに50万円上乗せされます。また、一般型通常枠では、一定の賃上げ要件を満たした場合に補助上限額が150万円引き上げられます。
申請枠が変更されているため、申請をご希望の事業者様は当社トライズコンサルティングまでご相談ください。当社は小規模事業者持続化補助金の申請のコツを熟知しており、サポートした案件で高い採択率を誇っています。
中小企業省力化投資補助金
中小企業省力化投資補助金(中小企業省力化投資補助事業)は、2024年度に新たに誕生した補助金です。
これは、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等が行う省力化投資を支援する補助金です。中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることを目的としています。
中小企業省力化投資補助金には2025年から新設された「一般型」のほか、創設当初から設けられている「カタログ注文型」が存在します。「カタログ注文型」では事業者が投資対象を自由に選ぶのではなく、所定の「カタログ」にあらかじめ掲載された製品から投資対象を選ぶ申請枠です。
このカタログには、IoTやロボットなど、人手不足解消に効果がある汎用製品が掲載されています。公式ホームページに掲載されている「製品カタログ」に目を通すことで、補助対象となる製品のイメージがつかみやすくなるでしょう。
一方で、「一般型」では投資対象がカタログ掲載製品などに限定されません。自社用にカスタマイズされたオーダーメイド製品なども補助対象となるため、使い勝手がより向上したといえます。
中小企業省力化投資補助金の補助上限額は雇用する従業員数によって異なり、それぞれ次のとおりです。一定の賃上げ要件を達成した際は、補助上限額が上乗せされます。
| 申請類型 | 従業員数 | 補助上限額 (原則) | 補助上限額 (賃上げ要件達成時) | 補助率 |
| カタログ注文型 | 5名以下 | 200万円 | 300万円 | 1/2 |
| 6~20名 | 500万円 | 750万円 | ||
| 21名以上 | 1,000万円 | 1,500万円 | ||
| 一般型 | 5名以下 | 750万円 | 1,000万円 | ・補助金1,500万円まで:原則1/2、小規模・再生事業者は2/3 ・1,500万円超の部分:1/3 ・最低賃金引上げ要件達成時:2/3 |
| 6~20名 | 1,500万円 | 2,000万円 | ||
| 21~50名 | 3,000万円 | 4,000万円 | ||
| 51~100名 | 5,000万円 | 6,500万円 | ||
| 101名以上 | 8,000万円 | 1億円 |
トライズコンサルティングでは中小企業省力化投資補助金の申請サポート実績が豊富であり、申請のコツを熟知しています。申請をご希望の事業者様は、トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。
また、当社では補助金の受給を希望する事業者のほか、自社製品のカタログへの掲載を希望する事業者のサポートも行っています。受給をご希望の事業者様やカタログへ掲載をご希望の事業者様も、当社までお早めにご相談ください。
中小企業新事業進出補助金
中小企業新事業進出補助金とは、新規事業への挑戦を目指す中小企業の設備投資を促進する補助金です。2024年度をもって廃止された事業再構築補助金の後継として創設されました。既存の事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等が支援対象とされる補助金であり、2025年4月22日に第1回公募が開始されました。
中小企業新事業進出補助金の活用イメージは、次のとおりです。
- 機械加工業でのノウハウを活かし、新たに半導体製造装置部品の製造に挑戦する
- 医療機器製造の技術を活かして蒸留所を建設し、ウイスキー製造業に進出する
この中小企業新事業進出補助金に申請するには、中小企業等が、企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行い、次の基本要件をすべて満たす3年から5年の事業計画に取り組まなければなりません。
- 付加価値額の年平均成長率が+4.0%以上増加
- 「1人あたり給与支給総額の年平均成長率が、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上」または「給与支給総額の年平均成長率+2.5%以上増加」
- 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における地域別最低賃金+30円以上の水準
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等
申請する際には、これらの要件を満たすことを事業計画内で示すこととなります。
中小企業新事業進出補助金の補助率は、一律2分の1です。一方、補助上限額は従業員規模によって異なっており、それぞれ次のとおりです。
| 従業員数 | 補助上限額 |
|---|---|
| 21~50人 | 4,000万円(5,000万円) |
| 51~100人 | 5,500万円(7,000万円) |
| 101人以上 | 7,000万円(9,000万円) |
補助下限額はいずれも750万円に設定されており、あまり少額な投資では補助対象となりません。
また、カッコ内の金額は、大幅賃上げ特例適用事業者に適用される補助上限額です。大幅賃上げ事業者とは、事業終了時点で「事業場内最低賃金+50円」と「給与支給総額+6%を達成」の両方の要件を満たした事業者を指します。
中小企業新事業進出補助金は2025年度から新たに公募された補助金であり、2025年4月22日に第1回の公募が開始されました。申請をご希望の事業者様は、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。トライズコンサルティングは中小企業新事業進出補助金の前身である事業再構築補助金について豊富な実績を有しており、安心してお任せいただけます。
中小企業成長加速化補助金
中小企業成長加速化補助金とは、売上高100億円を目指す成長志向型の中小企業に対し、大胆な設備投資を支援する補助金です。活用イメージとしては、次のものなどが想定されています。
- 工場、物流拠点などの新設・増築
- イノベーション創出に向けた設備の導入
- 自動化による革新的な生産性向上
中小企業成長加速化補助金は「売上高100億円」がキーワードとなっており、申請するには次の要件などをすべて満たさなければなりません。
- 投資額(建物費、機械装置費、ソフトウェア費の補助対象経費の合算金額)が1億円以上(税抜)であること
- 補助金の公募の申請時までに補助事業者の「100億宣言」が「100億宣言ポータルサ
- イト」に公表がされていること(1次公募においては、補助金の公募申請と同時に100億宣言の申請が可能)
- 一定の賃上げ要件を満たす今後5年程度の事業計画を策定すること
- 日本国内において補助事業を実施すること
この「100億宣言」とは、成長ビジョンを示し国の支援や同じ志の経営者ネットワークも活かして、目標の実現を目指すものです。次の内容などを中小企業が自ら宣言し、2025年5月に開設予定のポータルサイト上で公表します。
- 企業概要
- 企業理念・経営者の意気込み
- 売上高100億円実現の目標と課題
- 売上高100億円に向けた具体的措置(取り組み)
中小企業成長加速化補助金の補助上限額は5億円、補助率は2分の1です。補助上限額が非常に高額に設定されているため、100億円企業を目指す中小企業はこの補助金を活用できないか確認しておくとよいでしょう。
中小企業成長加速化補助金は、2025年3月に第1回の公募が開始された新しい補助金であるため、申請にあたっては専門家のサポートを受けることが採択を勝ち取るコツといえます。
当社トライズコンサルティングでは補助金の申請サポート実績が豊富であり、申請のコツを熟知しています。中小企業成長加速補助金への申請をご希望の事業者様は、トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。
大規模成長投資補助金
大規模成長投資補助金とは、地域の雇用を支える中堅・中小企業が足元の人手不足等の課題に対応し、成長していくことを目指して行う大規模投資を促進する補助金です。地方における持続的な賃上げを実現することを目的としています。
大規模成長投資補助金の補助上限額は、これまでになく高額の50億円(補助率は3分の1)です。ただし、少額の事業投資は補助対象とはならず、申請をするには次の要件などを満たさなければなりません。なお、従来とは賃上げ要件の考え方が変更されていることにご注意ください。
- 投資額10億円以上(専⾨家経費・外注費を除く補助対象経費分)であること
- 賃上げ要件(補助事業の終了後3年間の対象事業に関わる従業員等1⼈当たり給与⽀給総額の年平均上昇率が、全国の過去3年間の最低賃⾦の年平均上昇率である4.5%以上)を満たすこと
- 中堅・中小企業(常時使用する従業員数が2,000人以下の会社等)であること
大規模成長投資補助金は申請のハードルこそ高いものの、その分だけリターンも桁違いに大きな補助金といえます。事業を飛躍させるため大規模な事業投資を検討している場合には、大規模成長投資補助金が活用できないか確認するとよいでしょう。
非常に大型の補助金であるため、採択を勝ち取るには補助金制度を熟知した専門家のサポートを受けることをおすすめします。
当社トライズコンサルティングでは補助金の申請サポートについて豊富な実績を有しており、特に大型補助金への申請を得意としています。大規模成長投資補助金への申請をご希望の事業者様は、トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。
事業承継・M&A補助金
事業承継・M&A補助金とは、事業承継に際しての設備投資やM&A・PMI(M&A後の経営統合)の専門家活用費用等を支援する補助金です。これまでは「事業承継・引継ぎ補助金」との名称で公募がされてきたものの、2025年度からは「事業承継・M&A補助金」へと名称が変更されました。
2025年度における事業承継・M&A補助金の申請枠は、次のとおりです。
- 事業承継促進枠:5年以内に事業承継を予定している場合の、設備投資等に係る費用を補助する枠
- 専門家活用枠:M&A時の専門家活用に係る費用(フィナンシャル・アドバイザーや仲介に係る費用、表明保証保険料等)を補助する枠
- PMI推進枠:PMIに係る費用(専門家費用、設備投資等)を補助する枠
- 廃業・再チャレンジ枠:事業承継・M&Aに伴う廃業等に係る費用(原状回復費・在庫処分費等)を補助する枠(他の一定の申請枠との併用が可能)
補助上限額と補助率は、それぞれ次のとおりです。
| 申請枠 | 類型 | 補助上限額 | 補助率 |
| 事業承継促進枠 | 800万円(賃上げ要件を満たす場合は1,000万円) | 1/2(小規模事業者は2/3) | |
| 専門家活用枠 | 買い手支援類型 | 600万円(DD費用も申請する場合は+200万円、廃業費も申請する場合は+150万円) | 2/3 |
| 売り手支援類型 | 1/2(赤字・営業利益率の低下に該当する場合は2/3) | ||
| PMI推進枠 | PMI専門家活用類型 | 150万円 | 1/2 |
| 事業統合投資類型 | 800万円(一定の賃上げ要件を満たす場合は1,000万円) | 1/2(小規模事業者は2/3) | |
| 廃業・再チャレンジ枠 | 150万円 | 1/2・2/3(他の枠と併用する場合はその枠の補助率に従う) | |
事業承継・M&A補助金は申請枠などが大きく変更されているため、申請する際は専門家のサポートを受けるとよいでしょう。
当社トライズコンサルティングは事業承継・M&A補助金(旧:事業承継・引継ぎ補助金)のサポート実績が豊富であり、採択した案件で高い採択率を誇っています。申請をご希望の事業者様は、トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。
2025年(令和7年)6月時点の補助金最新情報
2025年6月時点において、各補助金の公募状況はどのようになっているのでしょうか。それぞれの補助金について、最新情報を紹介します。
ものづくり補助金
ものづくり補助金は2025年6月現在、第20回の公募期間中です。公募スケジュールは、次のとおりです。
- 公募開始:2025年4月25日
- 申請受付開始日:2025年7月1日(火)
- 申請締切:2025年7月25日(金)17:00
ものづくり補助金の第20回公募への申請をご希望の際は、トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。早めから準備に取り掛かることで申請内容のブラッシュアップが可能となり、採択を勝ち取りやすくなります。
事業再構築補助金
事業再構築補助金は2025年3月26日に締め切られた第13回公募をもって廃止されており、新たに申請することはできません。申請をご希望の事業者様は、「中小企業新事業進出補助金」など、他の補助金の活用を検討するとよいでしょう。
なお、当社トライズコンサルティングは事業再構築補助金の採択後に必要となる「交付申請」や「実績報告」などのサポートを行っています。これらの手続きでお困りの際は、トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。
IT導入補助金
2025年6月現在、IT導入補助金は公募期間中です。公募締切は、それぞれ次のとおりです。
- 通常枠・インボイス枠・セキュリティ対策推進枠の第3次締切分:2025年7月18日(金)17:00
- 複数社連携IT導入枠の第2次締切分:2025年8月20日(水)17:00
なお、通常枠とインボイス枠、セキュリティ対策推進枠は切れ目のない公募が実現されており、第3次の締切の後は、すぐに第4次への申請が可能となります。一方で、複数社連携IT導入枠は次回以降のスケジュールが公表されていないため、ご希望の際は現在公募中の第2次に間に合うよう準備を進めるとよいでしょう。
申請をご希望の事業者様は、当社トライズコンサルティングまでお早めご相談ください。
小規模事業者持続化補助金
2025年6月現在、小規模事業者持続化補助金のうち「一般型通常枠」は、次のスケジュールで第17回の公募が締め切られており、すぐに申請することはできません。
- 公募要領公開:2025年3月4日(火)
- 申請受付開始:2025年5月1日(木)
- 申請受付締切:2025年6月13日(金)17:00(事業支援計画書の発行受付締切:2025年6月3日)
また、「一般型災害支援枠」は第7回の公募期間中です。公募スケジュールは、次のとおりです。
- 公募要領公開:2025年4月30日(水)
- 申請受付開始:2025年5月16日(金)
- 申請受付締切:2025年7月28日(月)(支援機関確認書発行の受付締切:2025年7月18日)
一方で、「創業型」と「共同・協業型」、「ビジネスコミュニティ型」も公募が締め切られたばかりです。前回の締切は、「創業型」と「共同・協業型」は2025年6月16日、「ビジネスコミュニティ型」は2025年6月2日でした。
当社トライズコンサルティングは、小規模事業者持続化補助金の申請サポートについて豊富な実績を有しており、これまでも多くの採択を勝ち取ってきました。小規模事業者持続化補助金への申請をご希望の事業者様は、トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。
中小企業省力化投資補助金
中小企業省力化投資補助金のうち「カタログ注文型」は、2025年6月下旬現在、申請が随時受け付けられています。つまり、当面の間は事業者様にとって都合のよいタイミングで、いつでも申請することが可能な状態にあるということです。
2024年6月25日に開始された第1回公募では、中小企業省力化投資補助金にも申請締切が設けられていました。しかし、応募や交付申請の利便性向上を図り、早期の省力化を実現することを目的として、2024年8月9日から随時受付へと変更されています。
一方で、「一般型」へはすぐに申請することはできません。ただし、間もなく第3回公募が開始される予定です。第3回の公募スケジュールは、次のとおりです。
- 公募開始日:2025年6月中旬(予定)
- 申請受付開始日:2025年8月上旬(予定)
- 公募締切日:2025年8月下旬(予定)
申請をご希望の事業者様は、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。当社は補助金申請のコツを熟知しているため、ご依頼いただくことで採択の可能性を高めることが可能となります。
また、当社ではカタログへの掲載を希望する事業者様の支援も行っています。カタログへの掲載を希望する事業者様も、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。
中小企業新事業進出補助金
2025年4月22日、中小企業新事業進出補助金の第1回公募が開始されました。第1回の公募スケジュールは、次のとおりです。
- 公募要領公開:2025年4月22日(火)
- 申請受付開始:2025年6月17日
- 公募締め切り:2025年7月10日(木)18:00まで
締切が間近に迫っているため、申請をご希望の事業者様は、早急に準備に取り掛かることをおすすめします。
当社トライズコンサルティングは中小企業新事業進出補助金の前身である事業再構築補助金について豊富な実績を有しており、多くの採択を勝ち取ってきました。中小企業新事業進出補助金への申請をご希望の事業者様は、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。
中小企業成長加速化補助金
2025年6月現在、中小企業成長加速化補助金は第1回目の公募が締め切られたばかりであり、すぐに申請することはできません。公募スケジュールは、次のとおりでした。
- 募集開始日時:2025年5月8日 16:00
- 募集終了日時:2025年6月9日 17:00
中小企業成長加速化補助金への申請をご希望の事業者様は、当社トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。当社は大型補助金への申請サポートについて豊富な実績を有しています。
大規模成長投資補助金
2025年6月現在、大規模成長投資補助金は次のスケジュールで第3次の公募が締め切られたばかりであり、申請することはできません。
- 公募開始:2025年3⽉10⽇(⽉)
- 公募締切:2025年4⽉28⽇(⽉)
大規模成長投資補助金の採択を勝ち取るには、申請内容を入念に練り込まなければなりません。申請をご希望の事業者様は今後の情報を待ちつつ、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。
トライズコンサルティングは補助金の申請サポート実績が豊富であり、サポートした案件で多くの採択を勝ち取ってきました。また、プレゼンテーション審査に備えたアドバイスも可能です。
事業承継・M&A補助金
2025年6月現在、事業承継・M&A補助金へすぐに申請することはできません。
申請をご希望の事業者様は今後の情報を待ちつつ、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。トライズコンサルティングは事業承継・M&A補助金の前身である事業承継・引継ぎ補助金について豊富なサポート実績を有しており、多くの採択を勝ち取ってきた実績があります。
補助金の申請に関するよくある質問
補助金に興味があっても、不明点が多く活用をためらうこともあるでしょう。ここでは、補助金に関するよくある質問とその回答を紹介します。
補助金が採択されたらすぐにお金が振り込まれる?
誤解している人も少なくありませんが、補助金が採択されたからといってすぐにお金が振り込まれるわけではありません。補助金が振り込まれるまでには、採択後にまず交付申請を行い、その後自己資金や借入金などで補助対象事業を実施し、その実績報告を行うなどのステップが必要です。
補助金を受け取るまでには長い道のりが必要であることから、専門家にサポートを依頼する際は、補助金が振り込まれる最後の段階までサポートしてくれる専門家を選ぶようにしてください。
補助金の申請はいつでもできる?
補助金の申請はいつでもできるわけではなく、補助金ごとに定められた公募期間中にのみ行うことができます。また、補助金制度は永続的なものではなく、今年度に存在する補助金が翌年度にはなくなってしまうケースや、要件や補助上限額などが変わることも珍しくありません。
そのため、自社に合った補助金を見つけたら「数年後に申請しよう」などと考えるのではなく、早期に申請に取り掛かるようにしてください。
補助金が不採択だった場合はどうすれば良い?
補助金が不採択となった場合は、次回の公募回に再度チャレンジすることが可能です。しかし、不採択となった申請書をそのまま使いまわしても、採択される可能性はほとんどありません。
そのため、不採択となった場合は再度事業計画を練り直し、申請書類を作り直すことが必要です。また、補助金によっては事務局へ問い合わせることで不採択となった理由を教えてもらうことができるため、この回答を踏まえて計画を練り直すとよいでしょう。 しかし、不採択理由の確認や事業計画の練り込みなどを自社のみで行うことは容易ではありません。そのため、不採択となった場合はその補助金に強い専門家へ相談し、専門家のサポートを受けつつ再申請に臨むようにしてください。
補助金の申請代行はトライズコンサルティングへ!
補助金の申請代行(サポート)は、トライズコンサルティングにお任せください。豊富な実績と経験のもと、貴社の抱える課題を解決し、求める成果にコミットします。
当社には各種業界に精通し、補助金申請のコツも押さえた優秀な専門家が在籍しているため、実現可能性の高い事業計画策定の支援が可能です。設備投資に必要な資金調達や補助金採択後の報告作業など包括的なサポート体制も構築しています。
補助金の申請代行(サポート)のご相談先をお探しの場合は、ぜひトライズコンサルティングまでお気軽にお問い合わせください。
まとめ
補助金を申請して採択を勝ちとるコツを解説するとともに、2025年6月時点における主要な補助金の最新情報を紹介しました。
2025年度は新たに創設された補助金も多く、中には非常に大型の補助金も存在します。自社の成長スピードを早めるため、これまで補助金を活用したことのない事業者様も補助金の活用を検討するとよいでしょう。
とはいえ、自社だけで申請して補助金の採択を得ることは容易ではありません。採択の可能性を高めるためには、実績豊富な専門家のサポートを受けることをおすすめします。補助金制度を熟知した専門家にサポートを受けて申請内容を練り込むことが、採択を勝ち取るコツといえるでしょう。
また、早めから専門家にコンタクトをとっておくことも、補助金申請のコツといえます。早めから相談をすることで公募開始などの最新情報を得やすくなるうえ、申請内容のブラッシュアップにも十分な時間をかけやすくなるためです。
当社トライズコンサルティングは補助金の申請サポートについて豊富な実績を有しており、採択を勝ち取る申請のコツやポイントなどを熟知しています。コツを踏まえた補助金申請サポートをご希望の事業者様や自社の取り組みに活用できる補助金を知りたい事業者様は、トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。
補助金の活用に関する初回のご相談は、無料です。また、Zoomなどのオンラインツールを活用しているため、全国どこからでもご相談・ご依頼いただけます。