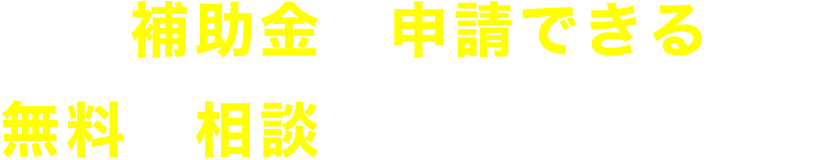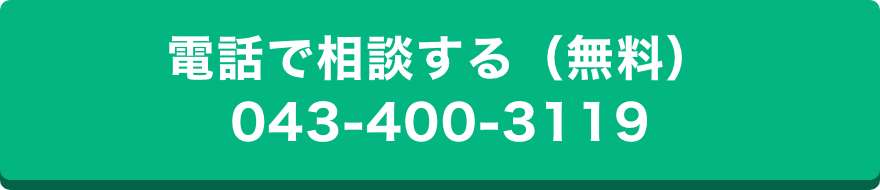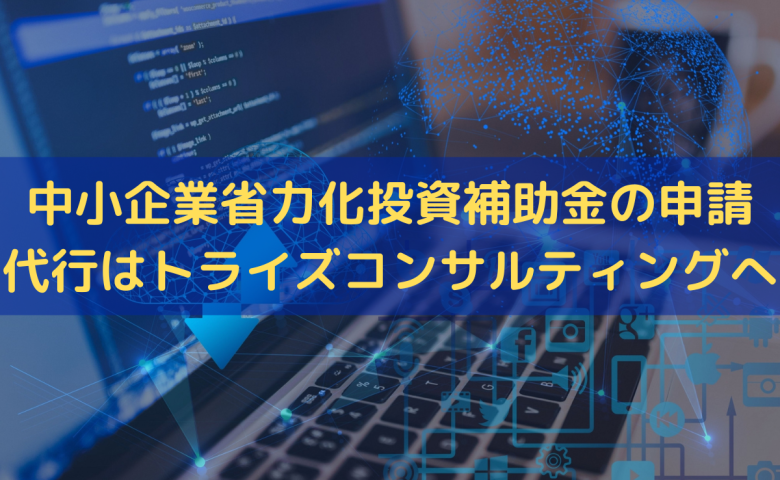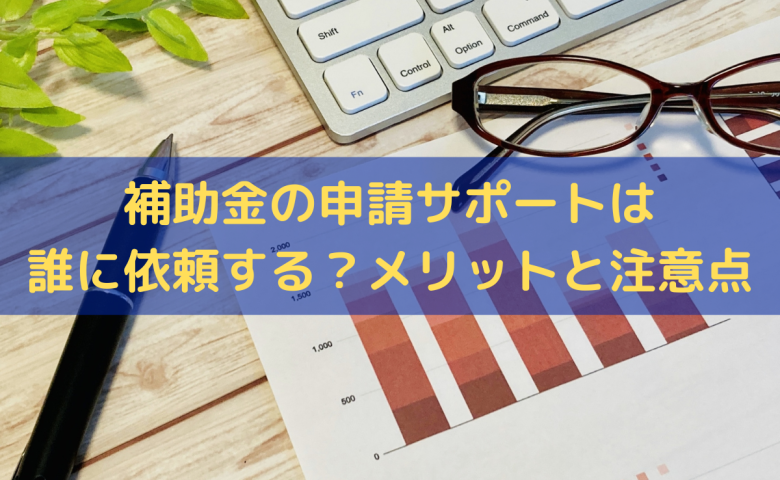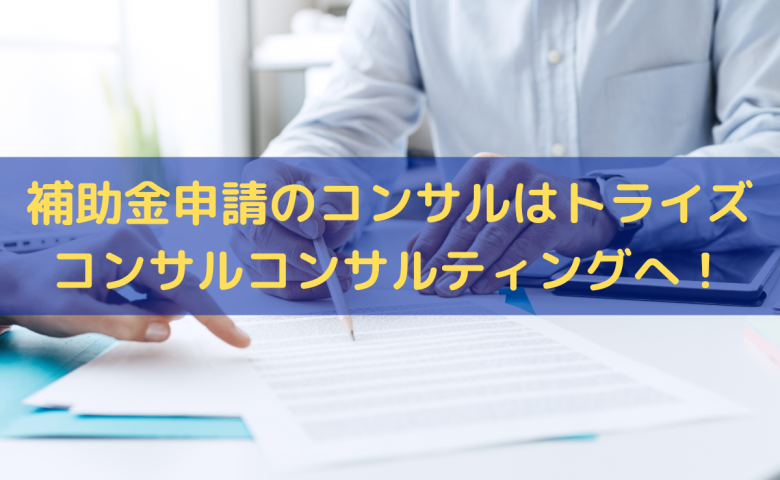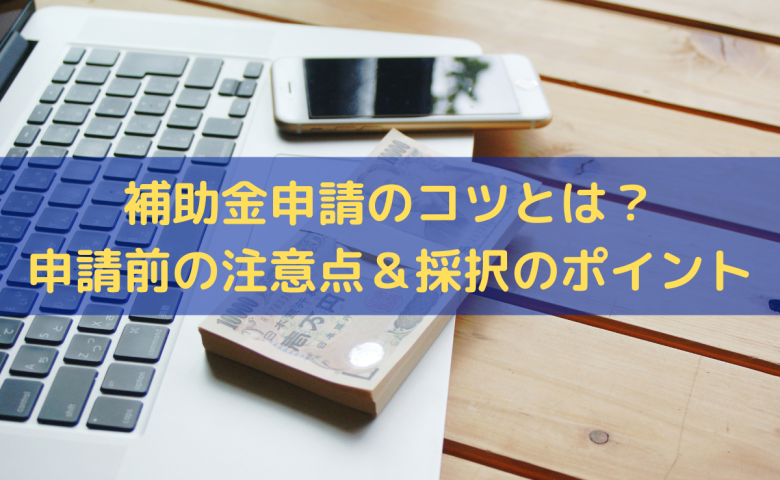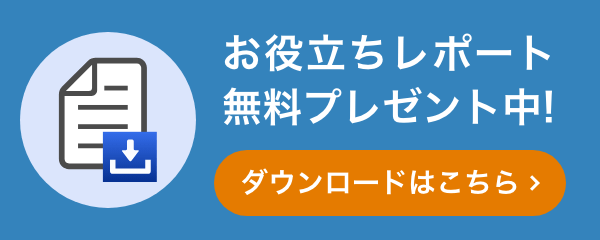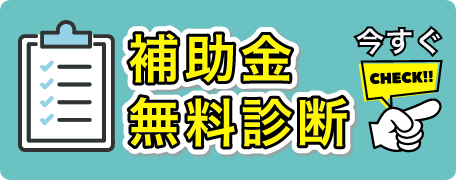補助金とは、国や地方公共団体などからまとまった事業資金を得られる制度です。なかには非常に高額な補助金が受け取れる制度もあるうえ、融資とは異なり、原則として返済は必要ありません。そのため、返済余力を残すことなく思い切った事業投資が可能となります。補助金をうまく活用することで、事業の成長速度を格段に早めることにつながるでしょう。
ただし、補助金は申請要件を満たして期限内に申請したからといって、必ずしも受給できるものではありません。補助金を受け取るには、多数の申請の中から交付対象に相応しいとして選ばれる(採択される)必要があります。特に大型の補助金では多くの事業者が採択を目指して申請内容を練り込むため、自力で採択を勝ち取るハードルは高くなる傾向にあります。
そこでおすすめなのが、補助金にくわしい専門家による代理申請の活用です。専門家からコンサルティングを受けて申請内容を練り込むことで、採択の可能性を高めることが可能となります。また、自社で要する手間や時間を最小限に抑えることができるでしょう。
では、補助金の代理申請や申請サポートは、誰に依頼すればよいのでしょうか?また、2025年6月時点で公募されている補助金には、どのようなものがあるのでしょうか?今回は、補助金の代理申請についてくわしく解説するとともに、2025年6月時点における主要な補助金の最新情報を紹介します。
なお、補助金は本来「代理で」申請できるようなものではなく、事業者様自身が自社の責任で申請すべきものです。そのため、実際に専門家が代理で申請するものではありません。ただし、「代理申請」で検索している人も多いため、この記事では専門家による補助金の「申請サポート」のことを「代理申請」と称しています。
当社トライズコンサルティングは、補助金の代理申請や申請サポートについて豊富な実績を有しています。トライズコンサルティングとは、中小企業診断士である野竿が代表を務めるコンサルティング会社です。自社に合った補助金が知りたい際や専門家による申請サポートをご希望の際は、トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。
補助金とは
まず、補助金の特徴について解説します。
補助金は、主に国や地方自治体から中小企業に対して募集され、売上の拡大や生産性の向上につながる取り組みに要した費用の一部を金銭的に支援するものです。実施主体の趣旨に沿った取り組みが対象となり、制度ごとにその内容は異なっています。
補助金と似た制度に「助成金」があります。
助成金との違い
補助金と似た制度として助成金が挙げられますが、両者には明確な違いがあります。最も大きな違いは、要件を満たしていれば受け取れるか否かという点です。
助成金の場合、申請の条件を満たし、必要書類を提出すれば受けることができます。申請についても、期限内に提出するとすぐに審査が行われ、問題がなければ助成金が支給されるという流れになっています。そのため、予算に達してしまった場合、受給できないこともあり、早い者勝ちという側面を持つ制度もあります。
これに対して補助金は期限まで申請を受け付けており、期限後に提出された事業計画書などが審査員によって採点され、点数の高い順に採択されるという流れになっています。そのため、期限内に申請をしたからといって、必ずすべての事業者が補助金を受給できるというわけではありません。
ここでは、補助金と助成金の違いについて、3つ具体例を挙げて解説します。
補助金には事業計画が必要
補助金の申請には、事業計画の策定が必須となっています。補助金を活用して取り組む事業について、具体的な数値や根拠を示し、将来展望まで見据えた計画書を作成する必要があります。
中小企業向けの補助金の中でも難易度の易しい「小規模事業者持続化補助金」であっても、A4サイズで5枚程度の作成を求められ、補助金額が1,000万円を超えるような「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」などの場合では、10~15枚必要になります。
求められる計画書の枚数はあくまでも目安ではありますが、最低でも求められる枚数の8割以上は作成しなければ採択されることは難しいでしょう。そんなに多くの計画書を作るのは大変と思われるかもしれませんが、実際に作成してみると意外と枚数が足りないといったこともあります。
一方、助成金は制度ごとに設定された売上高の過年度比較や労働者の賃上げの上昇率などの要件を満たすことを示す証拠書類を提出するだけで申請することができます。決算書などのすでに作成されている書類やフォーマットの決まった書類を準備する場合がほとんどのため、補助金と比較して申請が容易です。
補助金には審査がある
補助金は申請された後、事務局によって事業計画の審査が行われます。委託された外部の専門家によって点数が付けられ、得点の高い順に採択者が決定されるというシステムになっており、結果の公表までは2~3か月程度を要します。
採択率は、制度や実施された年度によっても異なりますが、おおむね30〜60%ほどとなっています。つまり、事業計画書をはじめとした申請書類を準備し申請を行っても、半分近くは採択されないということです。そのため、かけた時間や手間が無駄になってしまうこともあり得ます。
一方、助成金に関してはこういった審査はなく、申請した書類により、受給の要件を満たしているかが確認されます。
このような違いは、補助金・助成金それぞれの財源が異なっていることが主な理由です。助成金は主に会社と労働者が折半して納める雇用保険料が財源となっているのに対し、補助金の財源は国民が納める税金です。そのため、より厳正な審査が必要となり、支給する会社を選別しなくてはならないからと考えられます。
補助金は手続きが煩雑
補助金を受給するまでの手続きは大変煩雑です。大きく「補助金の申請まで」「採択の発表以降」「補助金の受給以降」の3ステップに分けることができ、それぞれの段階で公募要領や手引きに即した手続きを踏む必要があります。
補助金の申請まで
まず、補助金には制度ごとに趣旨や目的が異なっているため、数多くの制度の中から貴社の取組みにマッチしたものを見つける必要があります。その後、公募要領を理解し、事業計画の策定、その他の必要書類を準備し、ようやく申請することができます。
採択の発表以降
次に採択が発表された後、改めて補助金の使途を確定させる交付申請を行い、補助事業に取組みます。このとき、時流の変化などにより、事業計画とは異なった動きをする場合は必ず事務局へ確認し、必要があれば変更申請をする必要があります。
補助事業の取り組みがすべて完了したら、成果を報告書にまとめて、事務局に実績報告を行います。実績報告が一度で承認されることは少なく、修正のため、何度か事務局とやり取りをすることになるでしょう。
補助金の受給以降
実績報告が承認されて、補助金を受給した後も手続きが必要な場合があります。「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」では、策定した3〜5年の計画期間の間、事業の状況報告を継続して行わなければなりません。また、国等が政策立案のために実施する調査にも可能な範囲で協力を求められます。
補助金の代理申請とは
補助金の代理申請(サポート)とは、補助金に精通した専門家が、中小企業等の行う補助金の申請を支援することです。
補助金は、税金を財源に返済不要の資金を支給するため、不正受給者を出さないよう非常に厳正な仕組みとなっています。そのため、中小企業が自社のみで手続きを行うことはハードルが高く、処理に手間取り、最悪、採択された補助金を受給できない可能性もあります。
補助金の代理申請(サポート)を利用することでこうした事態を防ぎ、申請自体もスムーズに行うことができます。
補助金の代理申請は違法になる?
補助金の代理申請は、違法かどうか気になる場合もあるでしょう。
結論をお伝えすると、補助金の代理申請は違法ではありません。ただし、一部の補助金事務局で、代理申請をよしとしない風潮があることもまた事実です。
補助金の代理申請や申請サポートを依頼する際は、その補助金を熟知した専門家と相談したうえで、サポートを受ける範囲や方法などについてあらかじめすり合わせをするようにしてください。
補助金の虚偽申請は違法
補助金の代理申請は違法ではない一方で、補助金の虚偽申請は違法です。まっとうな専門家であれば、事業者に虚偽申請をそそのかすようなことはありません。
一方で、新型コロナ禍における給付金で確定申告書を偽造するなどし、多くの逮捕者が出たことは記憶に新しいのではないでしょうか?残念なことに、補助金のサポートをする民間コンサルタントの中には、虚偽申請をそそのかす悪質な業者が混じっている可能性もあります。
そのような業者に依頼してしまわないよう、補助金の代理申請や申請サポートを依頼する専門家はよく選定することが必要です。そのうえで、業者から虚偽申請をそそのかされたとしても、絶対に応じないようにしてください。
虚偽申請が発覚すれば5年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくはこれらの併科に処される可能性があり、事業の運営どころではなくなる可能性が高いでしょう。
補助金の代理申請の依頼先
補助金の代理申請(サポート)は、意外と身近なところに依頼することができます。ここでは、中小企業様が依頼される可能性の高い5つの機関について解説します。
金融機関
金融機関は中小企業様にとって最も身近な存在であり、特にメインバンクであれば売上や業況など貴社の経営を理解しているため相談しやすいでしょう。
また、補助金は原則として実績報告が完了してからの後払いとなっているため、いったん業者に支払う資金を捻出する必要があります。そういったキャッシュフローについても金融機関で併せて相談することができるため、二度手間にならず、効率的に申請を行うことができます。
金融機関の場合、補助金の代理申請(サポート)への対応は大きく2パターンに分かれます。1つは、行員が担当するパターンです。この場合、担当する行員の資質や経験によって採択可能性が左右されます。
2つ目は、金融機関の連携している外部の専門家が対応するパターンです。この場合、採択可能性は高いと考えられますが、料金が別途かかる可能性があります。
税理士
税理士も中小企業様にとって身近な相談先でしょう。経理や決算を専門としており、貴社のお金の動きを最も把握している存在です。
補助金の申請に関しては、過去の売上推移や利益率などの分析が欠かせないため、長く付き合いのある税理士であれば補助金の代理申請(サポート)を依頼するのにうってつけの相手といえるでしょう。また、補助金で設備投資を行った際の圧縮記帳や特別償却などにも精通しているため、税務面でのフォローも期待することができます。
なお、税理士によっては、補助金にあまり明るくない場合もあります。貴社の契約している税理士が対応してくれるかは事前の確認が必要になるでしょう。
行政書士
行政書士は、行政に提出する書類の作成を代行する専門家です。補助金も申請書類を国や地方自治体などに提出するため、行政書士の領分といえるでしょう。
そのため、補助金の代理申請(サポート)を請け負っている行政書士も多く存在します。行政手続きに詳しいということに加え、補助事業で取り組む際に届出や許認可が必要になる場合、それらも併せて相談することができるという点が行政書士に代理申請(サポート)を依頼するメリットです。
なお、税理士同様、補助金に詳しくない行政書士もいるため、事前確認が必須です。特に、補助金の場合は、定型的な書類だけでなく、事業計画書の作成も必要となるため、そこをフォローしてもらえるかをよくチェックしておきましょう。
中小企業診断士
中小企業診断士は、経営のコンサルタント能力があることを示す唯一の国家資格で、事業戦略を立案する専門家です。ほとんどの中小企業診断士は補助金の代理申請(サポート)を請け負っており、相談もスムーズに進むでしょう。
補助金以外にも、中小企業様が活用できる支援施策について知見やノウハウを持っている場合が多いため、良きビジネスパートナーとなる可能性があります。
中小企業診断士は独占業務がないため、他の士業と比較して看板を掲げていることが少なく、探すことが困難である場合が多いです。金融機関から紹介された専門家や民間コンサルティング会社の担当がたまたま資格を保有していたという出会い方が多いかもしれません。
なお、これまでの実績や経験についてしっかりと確認しておくことが重要です。
民間コンサルティング会社
最後に紹介するのが、民間コンサルティング会社です。金融機関やその他業界の経験者、士業などの専門家が在籍していることが多く、貴社の取り組みに最もマッチした人材を派遣することが可能です。
また、補助金申請のノウハウが蓄積されているため、採択可能性の高い事業計画策定の支援サービスを受けることができるでしょう。そのため、貴社の補助金の採択に最もコミットするのが民間コンサルティング会社であるといえます。
注意点として、悪質な会社と契約をしてしまわないという点が挙げられます。近年、補助金の制度の充実を受け、代理申請(サポート)を謳う業者が数多く設立されました。大部分はまともな業者ですが、中には手数料を目的に不必要な補助金申請や設備投資をすすめるような業者もいます。事前に評判をよく調べてから相談するようにしてください。
助成金の場合は社会保険労務士のみ
主に厚生労働省が管轄する助成金において、代理申請(サポート)を行うことができるのは社会保険労務士のみとされています。なぜなら、補助金は主に税金を財源にしているのに対し、助成金はその財源が雇用保険料によって賄われており、雇用に関する制度が多いためです。
申請には労働に関する法律の知識が必要になり、雇用・賃上げに関する計画や就業規則等の修正を伴う場合が多く、社会保険労務士でないと対応することができません。
補助金の代理申請のメリット
補助金の代理申請を依頼することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?ここでは、専門家による代理申請や申請サポートを活用する主なメリットを3つ紹介します。
主なメリットは次のとおりです。
- 手続きを効率化できる
- 採択率を上げることができる
- コンサルティングを受けることができる
手続きを効率化できる
1つ目は、専門家へ依頼することで手続きを効率化できることです。
補助金の申請を自社ですべて行おうとすると、多大な手間と時間を要します。そして、補助金では経営の根幹に関わる情報を取り扱うことも多いため、経営陣が直接申請に関わることが少なくありません。
そのため、自社で補助金の申請をしようとすると、経営陣の貴重なリソースが補助金申請に多く割かれてしまいます。専門家に代理申請や申請サポートを依頼することで自社でかける手間や時間を最小限に抑えられ、本業に注力しやすくなります。
採択率を上げることができる
2つ目は、専門家へ依頼することで、採択される可能性が高まることです。
補助金の代理申請や申請サポートを行っている専門家は、補助金について熟知したうえで、申請書類の作成についての場数を踏んでいます。そのため、各補助金の審査員が知りたい内容が明確に記載された申請書類の作成が可能となり、採択率を高めることが可能となります。
専門家によるコンサルティングを受けることで、事業計画の精度が高まることも採択の可能性を引き上げることへとつながります。
コンサルティングを受けることができる
3つ目は、専門家によるコンサルティングを受けられることです。
大型の補助金を中心に、補助金の申請時には事業計画の提出が必要となります。この事業計画がどれだけ練り込まれているかが、採択のカギを握るといっても過言ではありません。
このコンサルティングは、補助金の採択を目指して行うものです。しかし、専門家によるコンサルティングを受けて作り込んだ事業計画は今後事業の方向性に悩んだ際の道しるべとなり、これ自体が企業の財産となり得ます。
補助金の代理申請のデメリット
補助金の代理申請を受けることには、デメリットもあります。主なデメリットを3つ紹介します。
- 報酬を支払う必要がある
- 採択後のサポートは含まれていない場合がある
- 悪質な業者を選んでしまう可能性がある
報酬を支払う必要がある
1つ目は、補助金の代理申請や申請サポートを依頼した場合、専門家に対して報酬の支払いが必要となることです。補助金の代理申請にまつわる専門家報酬は次で解説するとおり、着手金と成功報酬の二段階となっていることが一般的です。このうち、着手金はたとえ不採択になっても戻ってくるわけではありません。
採択後のサポートは含まれていない場合がある
2つ目は、専門家によるサポートが受けられるのは、原則として補助金を申請するまでであることです。
しかし、採択されたからといってすぐに補助金が振り込まれるわけではなく、その後も補助金を受け取るためには交付申請や実績報告などをしなければなりません。特に大型の補助金ではこの交付申請や実績報告にも手間がかかります。
中には採択後のサポートにも対応している専門家もいるため、自社で交付申請や実績報告を問題なく行う自信がない場合や手間を最小限としたい場合は、これらについてもサポートしている専門家を選ぶとよいでしょう。
なお、当社トライズコンサルティングでは、ご希望に応じて交付申請や実績報告についてもサポートしています。
悪質な業者を選んでしまう可能性がある
補助金の代理申請を行っている事業者のなかには、稀に悪質な業者が混じっていることがあります。
悪質な業者に依頼してしまうと、当初の案内とは異なる多額の報酬を請求される恐れがあるほか、粗悪な申請書類を作成され採択が遠のいてしまうかもしれません。また、申請要件を満たしていないにもかかわらず、虚偽申請を持ちかけられるリスクもあります。
悪質な業者に補助金の代理申請を依頼することのないよう依頼先についてはあらかじめおかしな評判が立っていないか調べ、料金についてはあらかじめ書面などで提示を受けることをおすすめします。
また、たとえそそのかされても、虚偽申請は絶対に行わないでください。補助金の虚偽申請は重大な犯罪であり、万が一行って発覚すれば前科が付くおそれがあります。
補助金の代理申請の費用・報酬相場
補助金の代理申請や申請サポートの費用相場や料金体系は、依頼先の専門家によって異なります。一般的には、「着手金」と「成功報酬」の2段階とされていることが多いでしょう。それぞれの概要や目安となる金額は次のとおりです。
着手金
着手金とは、専門家にサポートを依頼をした時点で発生する報酬です。
採択・不採択にかかわらず発生するものであり、たとえ不採択となっても原則として返金されません。
着手金の相場は申請する補助金の難易度等で異なり、「小規模事業者持続化補助金」のような比較的易しい制度の場合は着手金は低めに、「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」などの補助金額が大きい制度の場合は高めに設定されている傾向にあります。
金額の目安は、5万円から20万円程度です。
成功報酬
成功報酬とは、補助金が採択された場合に発生する報酬です。「採択された補助金額の〇割」との形で設定されていることが一般的です。
具体的な割合は補助金の種類や依頼先の専門家によって異なるものの、補助金額の10%から15%程度が目安といえるでしょう。
補助金の代理申請の選び方のポイント
補助金の代理申請や申請サポートの依頼先は、どのように選べば良いのでしょうか?ここでは、主な選び方を解説します。
- 実績があるかを調べる
- サポートの範囲を確認する
- 悪質な業者を避ける
実績があるかを調べる
補助金の代理申請や申請サポートの申請先は、実績のある専門家を選ぶようにしてください。実績のある専門家に依頼することで、申請へ向けたやり取りがスムーズとなるほか、採択を得られる可能性が高くなるためです。
サポート実績に自信がある場合は、顧客の守秘義務に反しない範囲で過去のサポート実績を教えてくれるはずです。また、自社ホームページでサポート実績を公表している場合も多いでしょう。
一方で、実績を尋ねると不機嫌になる専門家や頑なに実績を開示しようとしない専門家への依頼は、避けた方がよいかもしれません。
サポートの範囲を確認する
補助金の申請で手間や労力がかかるステップは、申請までのみではありません。補助金を申請して採択がされるとその後は「交付申請」や「実績報告」などが必要となることが多く、特に大型の補助金ではこれらにも多大な手間を要します。
中には、交付申請や実績報告にまで手が回らず、せっかく採択された補助金の受給を諦める事業者も存在するほどです。
そのため、補助金の代理申請や申請サポートを依頼する際は、申請までしかサポートを受けられないのか、それとも申請後の交付申請や実績報告などについてもサポートを受けられるのかなどについてあらかじめ確認しておくようにしてください。
悪質な業者を避ける
先ほど解説したとおり、補助金の代理申請や申請サポートを行う事業者には悪質な業者が混じっていることがあります。そのような悪質な業者を選んでしまわないよう注意が必要です。
悪質な業者への依頼を避けるため、サポート料金やサポート範囲は可能な限り書面など記録の残る方法での提示を求めることをおすすめします。また、悪質な業者であれば、インターネットで社名などで検索をかけた際に、よくない評価が見つかるかもしれません。 悪質は業者への依頼を避けるため、自身で防御することも必要です。
補助金の代理申請を依頼する場合の注意点
続いて、補助金の代理申請(サポート)について散見される勘違いを紹介します。代理申請(サポート)の利用を検討されている中小企業の方は、次の3点に注意してください。
- すべて丸投げはできない
- 断られる可能性もある
- 必ず採択されるとは限らない
すべて丸投げはできない
補助金の申請は、原則として中小企業側が主体的に取り組む必要があります。そのため、すべての業務を専門家へ委託することはできません。
補助金は、売上・利益を向上させる可能性のある中小企業の事業計画を根拠に支給されるものです。しかし、事業計画自体を他者がすべて作成しているとなれば、その信憑性は低くなるでしょう。
代理申請(サポート)は代行ではなく、あくまでも支援ということを念頭に置き、補助金の申請には能動的に取り組むようにしてください。
断られる可能性もある
補助金は常に受け付けられているわけではなく、申請期限があります。そのため、締切直前に代理申請(サポート)を依頼しても断られてしまう可能性があります。
補助金で採択を受けるためには、少なくとも数週間、難易度の高い制度であれば数ヶ月の準備が必要になるため、できるだけ早目に相談しましょう。また、特に実績のある専門家の場合、複数社から依頼を請けている可能性もあるため、手が回らないという理由で断られることもあります。
必ず採択されるとは限らない
補助金の代理申請(サポート)は、採択を約束するものではありません。自社のみで申請するよりも採択される可能性は高まるものの、補助金に審査がある以上、不採択となることもあります。
しかし、あくまでも補助金という制度の審査で不採択を受けただけで、貴社の事業計画がビジネス的に劣っているということではない点には注意してください。考え込まれた事業計画であれば、仮に補助金が採択されなくても実行すべきです。
補助金の代理申請の流れ
補助金の代理申請は、どのような手順で進んでいくのでしょうか?一般的な流れは次のとおりです。
- ヒアリング・資料提供
- 申請書の作成
- 電子申請・交付申請
- 補助事業の実施
- 実績報告・入金
ヒアリング・資料提供
専門家に補助金の代理申請や申請サポートを依頼すると、はじめに専門家からヒアリングがなされたり資料の提出を求められたりすることが一般的です。その公募回に間に合わせるため、資料はできるだけすみやかに提出することをおすすめします。
また、事業再構築補助金やものづくり補助金では、事業計画を練り込むため、このステップで専門家からのコンサルティングが受けられることも少なくありません。
申請書の作成
ヒアリングや資料をもとに、補助金の申請書類を作成します。補助金の申請書類は、専門家側で作成してくれることが一般的です。
電子申請・交付申請
申請書が作成できたら、その公募回の締め切りまでに申請を行います。最近では、補助金の申請は電子で行うことが一般的であり、書面での提出を受け付けない補助金も増えています。
その後申請が採択されたら、すみやかに所定の様式にて交付申請を行います。採択がされたからといってすぐに補助金が受け取れるわけではないため、誤解のないよう注意しましょう。
交付申請とはその補助金の交付を希望する旨の意思表示であり、補助金の申請とは別途行わなければなりません。この交付申請が事務局に受け付けられると交付決定がなされますが、この交付決定よりも前に支出した経費は補助対象とならないことが一般的であるため、交付申請は速やかに行うことをおすすめします。
補助事業の実施
交付申請後に、補助対象事業を実施します。この段階ではまだ補助金は入金されていないため、自己資金や金融機関からの借り入れなどで事業の実施資金を確保しなければなりません。補助金を活用する際は、全体でのお金の流れに特に注意が必要です。
実績報告・入金
補助事業を実施したら、補助金事務局へ実績報告を行います。その実績報告に問題がないと判断されると、ようやく補助金が交付されます。
補助事業の実施にあたって融資を受けていた場合は、金融機関との取り決めに従って早期に返済しておきましょう。
補助金の代理申請をトライズコンサルティングに依頼するメリット
補助金の代理申請や申請サポートの活用をご検討の際は、ぜひ当社トライズコンサルティングにお任せください。
ここでは、トライズコンサルティングに補助金の代理申請や申請サポートをご依頼いただく主なメリットを3つ解説します。
- コーチング等の手法を用いたコンサルティングを受けられる
- お金の流れの「見える化」支援も行っている
- 実現可能性の高い事業計画の作成をサポートしている
コーチング等の手法を用いたコンサルティングを受けられる
1つ目は、コーチングなどの手法を駆使したコンサルティングを受けられることです。
トライズコンサルティングの代表である野竿は中小企業診断士であり、中小企業の経営支援について確かな知識と経験を有しています。
しかし、その知識を上から押しつけるのではなく、クライアントの目標達成のためのコーチングやティーチング、ファシリテーションなどの手法を用いた伴走型のサポートを心がけています。
そのため、納得感のあるサポートが受けられると、多くの事業者様からご好評をいただいています。
お金の流れの「見える化」支援も行っている
2つ目は、お金の「見える化」など、補助金の申請以外のサポートも積極的に行っていることです。
トライズコンサルティングでは補助金の代理申請や申請サポートのみならず、中小企業の資金繰りへのコンサルティングも得意としています。
補助金を活用する中小企業は、資金繰りに余裕がないことも少なくありません。
当社によるコンサルティングを受けることで、会社のお金の流れが把握しやすくなり、資金繰りに余裕が生まれやすくなります。
実現可能性の高い事業計画の作成をサポートしている
3つ目は、実現可能性の高い事業計画の策定を支援していることです。
補助金の申請には事業計画書が必要となるため、申請にあたって急ごしらえで事業計画を策定する事業者様も多いことでしょう。
しかし、補助金の申請をきっかけとして事業計画書をしっかりと練り込んでおくと、補助金に採択される可能性が高まるのみならず、その後の事業運営の拠りどころともなります。
補助金を受け取ることはもちろん重要な目的であるものの、補助金の獲得後も事業は継続することでしょう。 そのため、トライズコンサルティングでは補助金獲得をゴールとするのではなく、補助事業の目標が達成され、貴社の成長に寄与することを目指してサポートを行っています。
2025年6月時点で利用可能なおすすめの補助金
補助金制度は非常に多く存在するうえ、年度や公募回によって改訂されることも少なくありません。また、情報が古いままとなっている専門家のホームページなども散見されます。
そのため、補助金について自力で調べれば調べるほど「今どのような補助金があり、どのような申請枠あるのか」「今ある補助金の金額はいくらなのか」などがわからず、混乱してしまうことでしょう。そこでここでは、2025年6月時点で存在するおすすめの補助金を紹介します。
より詳細な情報が知りたい場合や自社に合った補助金を知りたい場合などには、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。当社は補助金の代理申請実績が豊富であり、お問い合わせいただけましたら最適な補助金をご提案します。
- ものづくり補助金
- 事業再構築補助金
- IT導入補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 中小企業省力化投資補助金
- 中小企業新事業進出補助金
- 中小企業成長加速化補助金
- 大規模成長投資補助金
- 事業承継・引継ぎ補助金
ものづくり補助金
1つ目は、ものづくり補助金です。
ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた
新製品・新サービスの開発に必要な設備投資などを支援する補助金です。生産性向上や賃上げのための設備投資を計画している際は、ものづくり補助金の活用ができないか確認するとよいでしょう。
ものづくり補助金の申請枠と補助上限額、補助率は、それぞれ次のとおりです。前回公募から申請内容が改訂されているため、古い情報を参照しないようご注意ください。
| 申請枠 | 従業員規模 | 補助上限額 (下限は100万円) | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 製品・サービス高付加価値化枠 | 5人以下 | 750万円 | ・中小企業:1/2 ・小規模・再生:2/3 |
| 6~20人 | 1,000万円 | ||
| 21人~50人 | 1,500万円 | ||
| 51人以上 | 2,500万円 | ||
| グローバル枠 | - | 3,000万円 | ・中小企業:1/2 ・小規模:2/3 |
大幅な賃上げに取り組む場合には補助上限額がさらに100万円から1,000万円上乗せされます。また、最低賃金の引き上げに取り組む事業者は、補助率を2/3へと引き上げる措置の対象となります。
ものづくり補助金に申請するには、次の基本要件を満たす3~5年の事業計画に取り組まなければなりません。
- 付加価値額の年平均成長率が3.0%以上増加すること
- 次のいずれかに該当すること
- 1人あたり給与支給総額の年平均成長率が、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上である
- 給与支給総額の年平均成長率が2.0%以上増加すること
- 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準であること(最低賃金引上げ特例適用事業者以外)
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表などすること(従業員21名以上の場合のみ)
また、それぞれ次の要件を追加で満たす必要があります。
- 製品・サービス高付加価値化枠:革新的な新製品・新サービスの開発による高付加価値化
- グローバル枠:海外事業の実施による国内の生産性向上
当社トライズコンサルティングは、ものづくり補助金の代理申請(申請サポート)について豊富な採択実績を有しています。第19回公募への申請をご希望の事業者様は、当社までお早めにご相談ください。
事業再構築補助金
事業再構築補助金は、ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等が行う思い切った事業の再構築を支援対象とする補助金です。新型コロナ禍で誕生した補助金であるものの、新型コロナの収束とともに、制度の目的や申請要件などが変化してきました。
ただし、事業再構築補助金は2025年3月26日に締め切られた第13回公募をもって廃止されており、新たに申請することはできません。申請をご希望の事業者様は、事業再構築補助金の後継である「中小企業新事業進出補助金」など他の補助金の活用を検討するとよいでしょう。
なお、当社トライズコンサルティングでは採択後の交付申請や実績報告についてのサポートも可能です。事業再構築補助金に採択されたものの、採択後の手続きでお困りの際は、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。
IT導入補助金
IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者等が行う業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービスなど)の導入を支援する補助金です。
IT導入補助金とは導入するITツールを事業者が自由に選ぶのではなく、あらかじめ登録されたITツールの中から導入するツールを選ぶものです。複雑なITツールのみならず会計ソフトやPOSレジ、券売機などさまざまなツールが登録されています。
公式ホームページの「ITツール・IT導入支援事業者検索」から対象となるITツールを検索してみると、活用イメージが湧きやすくなるでしょう。
2025年度におけるIT導入補助金の申請枠と補助上限額は、それぞれ次のとおりです。
| 枠 | 通常枠 | インボイス枠 | 複数社連携IT導入枠 | セキュリティ対策推進枠 | ||||
| 類型 | 1プロセス以上 | 4プロセス以上 | 電子取引類型 | インボイス対応類型 | ||||
| 補助額 | 5万円~150万円 | 150万円~450万円 | 350万円 | ITツール | PC・タブレット等 | レジ・券売機等 | (1)インボイス対応型対象経費:左記同様 (2)消費動向等分析経費:50万円×グループ構成員数 (3)事務費・専門家費:200万円 ※(1)+(2)の上限は3,000万円 | 5万円~150万円 |
| ・1機能:~50万円 ・2機能以上:~350万円 | ~10万円 | ~20万円 | ||||||
| 補助率 | 1/2以内(最低賃金近傍の事業者は2/3) | ・大企業:2/3 ・中小企業:1/2 | ・~50万円:3/4(小規模事業者は4/5) ・~350万円:2/3 | 1/2 | ・(1):インボイス対応型と同様 ・(2)(3):2/3以内 | ・中小企業:1/2 ・小規模事業者:2/3 | ||
申請枠に大きな変更はないものの、セキュリティ対策推進枠の補助上限額が引き上げられているなど、細かな変更がなされています。
IT導入補助金は、2025年6月現在公募期間中です。具体的なスケジュールは、後ほど紹介します。申請をご希望の事業者様は、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金とは、商工会・商工会議所等と一体となって経営計画を作成し、その計画に基づいて行う販路開拓等の取り組みを支援する補助金です。
チラシの印刷費や広告出稿費、展示会の出展費用、ウェブサイト構築費用など小規模事業者がマーケティング活動に要する費用が広く補助対象とされており、非常に使い勝手のよい補助金であるといえます。また、他の補助金と比較して、申請の難易度もさほど高くありません。小規模事業者が新たな販路開拓に取り組む際は、小規模事業者持続化補助金の獲得にチャレンジするとよいでしょう。
小規模事業者持続化補助金は2025年度も引き続き公募されています。小規模事業者持続化補助金の申請枠と補助金額は、次のとおりです。
| 申請枠 | 補助上限額 | 補助率 | |
| 一般型 | 通常枠 | 50万円 | 2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4) |
| (インボイス特例) | (通常枠に50万円上乗せ) | ||
| (賃金引上げ特例) | (通常枠に150万円上乗せ) | ||
| 災害支援枠 | ・直接被害:200万円 ・間接被害:100万円 | 定額、2/3 | |
| 創業型 | 200万円(インボイス特例の適用あり) | 2/3 | |
| 共同・協業型 | 5,000万円 | ・地域振興等機関:定額 ・参画事業者:2/3 | |
| ビジネスコミュニティ型 | 50万円(2以上の補助対象者が共同で行う場合は100万円) | 定額 | |
一般型通常枠と創業型では、インボイス特例の要件を満たすことで、補助上限額がさらに50万円引き上げられます。また、一般形通常枠では、一定の賃上げ要件を満たす場合、補助上限額が150万円上乗せされることとなりました。
申請をご希望の事業者様は、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。当社は、小規模事業者持続化補助金の代理申請(申請サポート)について豊富な実績を有しています。
中小企業省力化投資補助金
中小企業省力化投資補助金は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して省力化投資を支援する補助金です。中小企業等の付加価値額や生産性向上を図ることで、賃上げにつなげることを目的としています。
この補助金には、「一般型」と「カタログ注文型」の2つの類型があります。
このうち、「一般型」は2025年に新たに設けられた類型です。補助対象が限定されておらず、省力化に寄与する製品が、オーダーメイド製品を含め広く補助対象とされます。
一方で、「カタログ注文型」は事業者が自由に投資する設備を選ぶのではなく、所定の「カタログ」に掲載された製品のなかから投資対象を選ぶ類型です。このカタログには、IoTやロボットなど、人手不足解消への効果が見込まれる汎用製品が掲載されています。公式ホームページに掲載されている「製品カタログ」に目を通すと、対象製品のイメージがつかみやすくなるでしょう。
補助上限額は従業員数によって異なっており、それぞれ次のとおりです。
| 類型 | 従業員数 | 補助上限額 (原則) | 補助上限額 (賃上げ要件達成時) | 補助率 |
|---|---|---|---|---|
| カタログ注文型 | 5名以下 | 200万円 | 300万円 | 1/2 |
| 6~20名 | 500万円 | 750万円 | ||
| 21名以上 | 1,000万円 | 1,500万円 | ||
| 一般型 | 5名以下 | 750万円 | 1,000万円 | ・補助金1,500万円まで:原則1/2、小規模・再生事業者は2/3 ・1,500万円超の部分:1/3 ・最低賃金引上げ要件達成時:2/3 |
| 6~20名 | 1,500万円 | 2,000万円 | ||
| 21~50名 | 3,000万円 | 4,000万円 | ||
| 51~100名 | 5,000万円 | 6,500万円 | ||
| 101名以上 | 8,000万円 | 1億円 |
この補助金は目的の1つに「賃上げ」が掲げられていることから、一定の賃上げ要件を達成した場合には、補助上限額が上乗せされます。
当社トライズコンサルティングでは中小企業省力化投資補助金の代理申請について豊富な実績を有しています。中小企業省力化投資補助金への申請をご希望の事業者様は、トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。
中小企業新事業進出補助金
中小企業新事業進出補助金とは、新規事業への挑戦を目指す中小企業の設備投資を促進する補助金です。既存の事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援するものであり、従来の事業再構築補助金に代わる制度と位置づけられています。
たとえば、次の場面での活用が想定されています。
- 機械加工業でのノウハウを活かし、新たに半導体製造装置部品の製造に挑戦する
- 医療機器製造の技術を活かして蒸留所を建設し、ウイスキー製造業に進出する
中小企業新事業進出補助金の補助率は一律で2分の1に設定されています。一方、補助上限額は従業員規模によって異なっており、それぞれ次のとおりです。
| 従業員規模 | 補助上限額 ※補助下限額は750万円 |
|---|---|
| 20人以下 | 2,500万円(3,000万円) |
| 21~50人 | 4,000万円(5,000万円) |
| 51~100人 | 5,500万円(7,000万円) |
| 101人以上 | 7,000万円(9,000万円) |
カッコ内の金額は大幅賃上げ特例適用事業者に適用される補助上限額であり、これは事業終了時点において次の2点を達成する事業者を指します。
- 事業場内最低賃金+50円
- 給与支給総額+6%
新事業への進出を目指す事業者様は、この中小企業新事業進出補助金の獲得を目指すとよいでしょう。また、新しい補助金であることから、申請をする際は専門家による代理申請や申請サポートの活用をおすすめします。
当社トライズコンサルティングでは、中小企業新事業進出補助金の前身である事業再構築補助金の代理申請(申請サポート)について豊富な実績を有しています。申請をご希望の事業者様は、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。
中小企業成長加速化補助金
中小企業成長加速化補助金とは、売上高100億円を目指す成長志向型の中小企業の大胆な設備投資を支援する補助金です。中小企業成長加速化補助金の補助上限額は5億円、補助率は2分の1です。非常に大型の補助金であるうえ建物費なども補助対象となることから、これを獲得できれば飛躍的な成長が実現しやすくなるでしょう。
「売上高100億円」がキーワードとなっており、補助金の公募の申請時までに「100億宣言」をすることなどが申請要件とされています。ただし、第1回の公募に限り、補助金の申請と同時に100億宣言の申請をすることが可能です。これを含めた主な申請要件は、次のとおりです。
- 補助対象経費のうち投資額が1億円以上(税抜)であること
- 補助金の公募の申請時までに補助事業者の100億宣言が100億宣言ポータルサイトに公表がされていること
- 一定の賃上げ要件を満たす今後5年程度の事業計画を策定すること
- 日本国内において補助事業を実施すること
「100億宣言」とは、中小企業が売上高100億円を超える企業になることや、それに向けたビジョン・取り組みなどを自ら宣言してポータルサイト上に公表をするものです。このポータルサイトはすでに開設されており、実際に各企業による100億宣言が閲覧できます。
この補助金の活用イメージは、次のとおりです。
- 工場、物流拠点などの新設・増築
- イノベーション創出に向けた設備の導入
- 自動化による革新的な生産性向上
中小企業成長加速化補助金も新しい補助金であることから、申請にあたっては専門家による代理申請や申請サポートの活用をおすすめします。
当社トライズコンサルティングは補助金の代理申請(申請サポート)実績が豊富であり、サポートした案件で高い採択率を誇っています。中小企業成長加速化補助金への申請をご希望の事業者様は、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。
大規模成長投資補助金
大規模成長投資補助金とは、中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等を支援する補助金です。地域の雇用を支える中堅・中小企業が足元の人手不足等の課題に対応し、成長していくことを目指して行う大規模投資を促進することにより、地方における持続的な賃上げを実現することを目的としています。
大規模成長投資補助金の活用イメージは、次のとおりです。
- 工場や倉庫、販売拠点の新設や増築
- 最先端の機械や省力化できる設備の購入
- ソフトウェアの購入や情報システムの構築
大規模成長投資補助金の補助上限額は50億円(補助率は3分の1)と、これまでになく非常に高額に設定されています。ただし、投資額10億円以上(専門家経費・外注費を除く)であることが要件とされており、少額の投資は補助対象とはなりません。また、賃上げが目的の1つであることから、次の賃上げ要件も課されています。
- 「補助事業の終了後3年間の対象事業に関わる従業員等1⼈当たり給与⽀給総額の年平均上昇率」が、「全国の過去3年間の最低賃⾦の年平均上昇率(4.5%)以上」であること
補助⾦の申請時に掲げた賃上げ⽬標を達成できなかった場合、未達成率に応じて補助⾦の返還が求められます。そのため、賃上げの覚悟を持って申請に挑まなければなりません。
思い切った投資をして飛躍的な成長を目指したい中堅・中小企業様は、大規模成長投資補助金の獲得を目指すとよいでしょう。非常に大型の補助金であることから、申請にあたっては専門家による代理申請や申請サポートの活用をおすすめします。
当社トライズコンサルティングは、補助金の代理申請について豊富な実績を誇っています。大規模成長投資補助金の獲得を目指したい事業者様は、当社までお早めにご相談ください。
事業承継・M&A補助金
事業承継・M&A補助金とは、中小企業の生産性向上や持続的な賃上げに向けて、事業承継に際しての設備投資やM&A・PMI(M&A後の経営統合)に要する専門家活用費用等を支援する補助金です。
これまでは「事業承継・引継ぎ補助金」との名称であったものの、2025年度からは「事業承継・M&A補助金」へと名称が変更されました。また、申請枠も改訂され、次の4つとなっています。
- 事業承継促進枠:5年以内に事業承継を予定している場合の設備投資等に要する費用を補助する枠
- 専門家活用枠:M&A時の専門家活用に要する費用(FAや仲介に係る費用、表明保証保険料など)を補助する枠
- PMI推進枠:PMI(M&A後の経営統合)に要する費用(専門家費用、設備投資等)を補助する枠
- 廃業・再チャレンジ枠(他の一定の枠と併用可能):事業承継・M&Aに伴う廃業等に要する費用(原状回復費・在庫処分費等)を補助する枠
なお、FA・仲介費用については、「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者による支援に係る費用のみ補助対象となります。
2025年度以降の補助上限額と補助率は、それぞれ次のとおりです。
| 申請枠 | 類型 | 補助上限額 | 補助率 |
| 事業承継促進枠 | 800万円(賃上げ要件を満たす場合は1,000万円) | 1/2(小規模事業者は2/3) | |
| 専門家活用枠 | 買い手支援類型 | 600万円(DD費用も申請する場合は200万円上乗せ、廃業費も申請する場合は150万円上乗せ) | 2/3 |
| 売り手支援類型 | 1/2(赤字・営業利益の率の低下に該当する場合は2/3) | ||
| PMI推進枠 | PMI専門家活用類型 | 150万円 | 1/2 |
| 事業統合投資類型 | 800万円(一定の賃上げ要件を満たす場合は1,000万円) | 1/2(小規模事業者は2/3) | |
| 廃業・再チャレンジ枠 | 150万円 | 1/2・2/3(他の枠と併用する場合はその枠の補助率に従う) | |
事業承継・M&A補助金は内容が大きく改訂されているため、申請する際は最新情報にご注意ください。申請にあたっては、専門家による代理申請や申請サポートの活用をおすすめします。
当社トライズコンサルティングでは、事業承継・M&A補助金(旧:事業承継・引継ぎ補助金)の代理申請(申請サポート)について豊富な実績を有しており、多くの採択を勝ち取ってきました。申請をご希望の事業者様は今後の情報を待ちつつ、トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。
2025年(令和7年)6月の補助金最新情報
2025年6月時点における、補助金の最新情報(スケジュール)を解説します。
ものづくり補助金
ものづくり補助金は2025年6月現在、次のスケジュールで第20回の公募期間中です。
- 公募開始:2025年4月25日
- 申請受付開始日:2025年7月1日(火)
- 申請締切:2025年7月25日(金)17:00
ものづくり補助金に申請するには、事業計画の策定・練り込みなどに相当の時間を要します。申請をご希望の事業者様は、できるだけ早期に当社トライズコンサルティングまでご相談ください。早めからご相談いただくことで申請準備に十分な時間がかけられ、採択を勝ち取りやすくなります。
IT導入補助金
IT導入補助金は2025年6月現在、それぞれ次のスケジュールで公募されています。
- 通常枠・インボイス枠・セキュリティ対策推進枠の第3次締切:2025年7月18日(金)17:00
- 複数社連携IT導入枠の第2次締切:2025年8月20日(水)17:00
なお、通常枠とインボイス枠、セキュリティ対策推進枠は第3次締切の後、すぐに第4次公募が控えています。切れ目のない公募が実現されており、自社の都合のよいタイミングで申請しやすいといえるでしょう。一方、複数社連携IT導入枠は次回以降の公募スケジュールが公表されていません。そのため、この枠への申請をご希望の際は、第1回の締切に間に合うよう申請準備を進めることをおすすめします。
当社トライズコンサルティングは、IT導入補助金の代理申請(申請サポート)実績が豊富であり、安心してお任せいただけます。IT導入補助金への申請をご希望の事業者様は、トライズコンサルティングへお気軽にご相談ください
小規模事業者持続化補助金
2025年6月現在、小規模事業者持続化補助金は「一般型通常枠」は次のスケジュールで公募が締め切られており、すぐにしんせいすることはできません。
- 公募要領公開:2025年3月4日(火)
- 申請受付開始:2025年5月1日(木)
- 事業支援計画書の発行受付締切:2025年6月3日(火)
- 申請受付締切:2025年6月13日(金)17:00
一方で、「一般型災害支援枠」は第7次の公募期間中です。スケジュールは、次のとおりです。
- 公募要領公開:2025年4月30日(水)
- 申請受付開始:2025年5月16日(金)
- 申請受付締切:2025年7月28日(月)(支援機関確認書発行の受付締切は2025年7月18日)
また、「創業型」と「共同・協業型」は2025年6月16日に、「ビジネスコミュニティ型」は2025年6月2日に公募が締め切られており、すぐに申請することはできません。
小規模事業者持続化補助金への代理申請や申請サポートをご希望の事業者様は、トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。当社トライズコンサルティングは小規模事業者持続化補助金の申請サポートについて豊富な実績を有しており、補助金の申請が初めての事業者様であっても安心してお任せいただけます。
中小企業省力化投資補助金
2025年6月現在、中小企業省力化投資補助金のうち「カタログ注文型」の申請は随時受け付けされています。第1回目は他の補助金と同様に期限を切って公募されていました。しかし、応募や交付申請の利便性向上を図り早期の省力化を実現するため、2024年8月9日からは随時申請へと切り替えられています。そのため、事業者様の都合のよいタイミングでの申請が可能です。
一方で、「一般型」は間もなく第3回の公募が開始される予定です。公式ホームページによると、第3回の公募スケジュールは次のとおりとされています。
- 公募開始日:2025年6月中旬(予定)
- 申請受付開始日:2025年8月上旬(予定)
- 公募締切日:2025年8月下旬(予定)
申請をご希望の事業者様は、当社トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。当社は、中小企業省力化投資補助金の代理申請や申請サポートについて豊富な実績を有しています。
また、当社はカタログへの掲載を希望する事業者様の代理申請や申請サポートも行っています。製品カタログへの掲載をご希望の事業者様も、トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。
中小企業新事業進出補助金
2025年4月22日に、中小企業新事業進出補助金の第1回公募が開始されました。第1回目の公募スケジュールは、次のとおりです。
- 公募要領公開:2025年4月22日(火)
- 申請受付開始:2025年6月17日(火)
- 公募締切:2025年7月10日(木)18:00
間もなく締切を迎えるため、申請をご希望の事業者様は早急に準備に取り掛かる必要があります。お困りの際は、当社トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。トライズコンサルティングは補助金の代理申請(申請サポート)を数多く手掛けており、中小企業新事業進出補助金の前身である事業再構築補助金について多くの採択を勝ち取ってきた実績があります。
中小企業成長加速化補助金
中小企業成長加速化補助金は、2025年6月現在、次のスケジュールで第1回の公募が締め切られたばかりであり、すぐに申請することはできません。
- 募集開始日時:2025年5月8日 16:00
- 募集終了日時:2025年6月9日 17:00
申請をご希望の事業者様は今後の情報を待ちつつ、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。事前にご相談いただくことで、公募開始の情報をいち早くお知らせすることが可能となります。
大規模成長投資補助金
2025年6月現在、大規模成長投資補助金は次のスケジュールで第3次公募が締め切られており、すぐに申請することはできません。
- 公募開始:2025年3⽉10⽇(⽉)
- 公募締切:2025年4⽉28⽇(⽉)
大規模成長投資補助金への申請をご希望の事業者様は、今後の情報を待ちつつ当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。トライズコンサルティングは補助金の代理申請(申請サポート)について豊富な実績を有しています。また、経営者様の出席が必要となるプレゼンテーション審査についてのアドバイスも可能です。
事業承継・M&A補助金
事業承継・M&A補助金のうち「専門家活用枠」は、2025年6月6日に第11次公募が締め切られており、すぐに申請することはできません。 また、その他の申請枠についても公募要領などは出されていない状況です。申請をご希望の事業者様は今後の情報を待ちつつ、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。
補助金の申請に関するよくある質問
補助金の申請には、ほかにもさまざまな疑問があることでしょう。ここでは、補助金の申請に関するよくある質問とその回答を紹介します。
補助金の申請資格の確認方法は?
補助金の申請資格(申請要件)を知る方法は、それぞれの補助金の公募要領や、事務局が運営するウェブサイトを確認することです。
申請要件は補助金によって異なるうえ、公募回によっても変動する可能性があります。そのため、補助金の申請準備に取り掛かる前に、必ず最新情報をご確認ください。
自社で調べても自社が申請要件を満たしているかどうか分からない場合などには、補助金事務局に直接問い合わせてみるほか、代理申請を依頼する専門家に相談することをおすすめします。
補助金の申請に必要な書類は?
補助金の申請に必要となる書類は、申請する補助金や申請枠などによって異なります。一般的な書類としては、次のものなどです。
- 事業計画書
- 財務諸表
- 売上高や従業員数の証明書
- 申請者の身分証明書
- 法人の登記簿謄本
ただし、これはあくまでも一例であるため、実際に申請する際はその補助金の最新の公募要領をよく確認してください。
補助金の申請にあたって注意するポイントは?
補助金を申請する際にまず注意すべきポイントは、補助金の趣旨や目的と、自社の取り組みがマッチしているかどうかです。たとえ素晴らしい事業計画であったとしても、補助金の目的から外れている場合は採択が遠のいてしまうためです。
また、公募要領をよく読んだうえで、申請要件や添付書類、記載事項などについて十分確認してください。せっかく申請しても要件を満たしていない場合は採択を受けることができないほか、添付書類や記載事項に漏れがあればそのまま不採択とされる可能性が高いためです。
補助金が不採択だった場合はどうすれば良い?
補助金が不採択となった場合、不採択の理由は通知されません。しかし、補助金事務局に問い合わせることで、不採択となった理由を教えてもらうことが可能です。
不採択となった理由を知ることで今後の申請に活かすことが可能となるため、可能な限り確認しておくことをおすすめします。また、代理申請などを利用せず自社で申請した結果不採択となった場合には、次回申請に向けて、専門家による代理申請や申請サポートの活用を検討するとよいでしょう。
補助金の代理申請はトライズコンサルティングにお任せください!
補助金の代理申請や申請サポートの活用をご検討の際は、ぜひ当社トライズコンサルティングまでご相談ください。当社は補助金の代理申請(サポート)に力を入れており、業界内でも高い水準の採択率を誇っています。
また、当社の代表者である野竿は中小企業診断士の資格を有しているほか、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関である「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」にも登録されており、安心してご相談頂くことが可能です。
当社はオンラインでのご相談にも対応しており、遠方の事業者様であっても、Zoomなどにてご相談いただけます。補助金の獲得を目指したい事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
補助金の代理申請を活用するメリット・デメリットや専門家を選ぶポイントなどを解説するとともに、2025年6月時点における補助金の最新情報を紹介しました。
補助金の申請をすべて自社だけで行おうとすれば、多大な時間と労力を要します。また、大型の補助金では競争率が高くなりやすく、自力で採択を受けるハードルは高いといえるでしょう。特に2025年度は新たに大型補助金も多く誕生しているほか従来の補助金も内容が改訂されており、自社に合った補助金を選定するだけでも一苦労です。
自社に合った補助金を的確に選定し採択を勝ち取るためには、専門家による代理申請や申請サポートの活用がおすすめです。補助金にくわしい専門家からコンサルティングを受けて申請内容を練り込むことで、採択の可能性を高めることにつながるでしょう。また、自社で割くべき時間や手間を最小限に抑えることも可能となります。
当社トライズコンサルティングは補助金の代理申請や申請サポートの実績が豊富であり、サポートした案件について高い採択率を誇っています。補助金の代理申請・申請サポートを依頼する専門家をお探しの際や、自社に合った補助金が知りたい際などには、当社トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。
補助金の活用や申請に関するご相談は、初回無料です。また、Zoomなどのオンラインツールを活用しているため、全国どこからでもご相談・ご依頼いただけます。