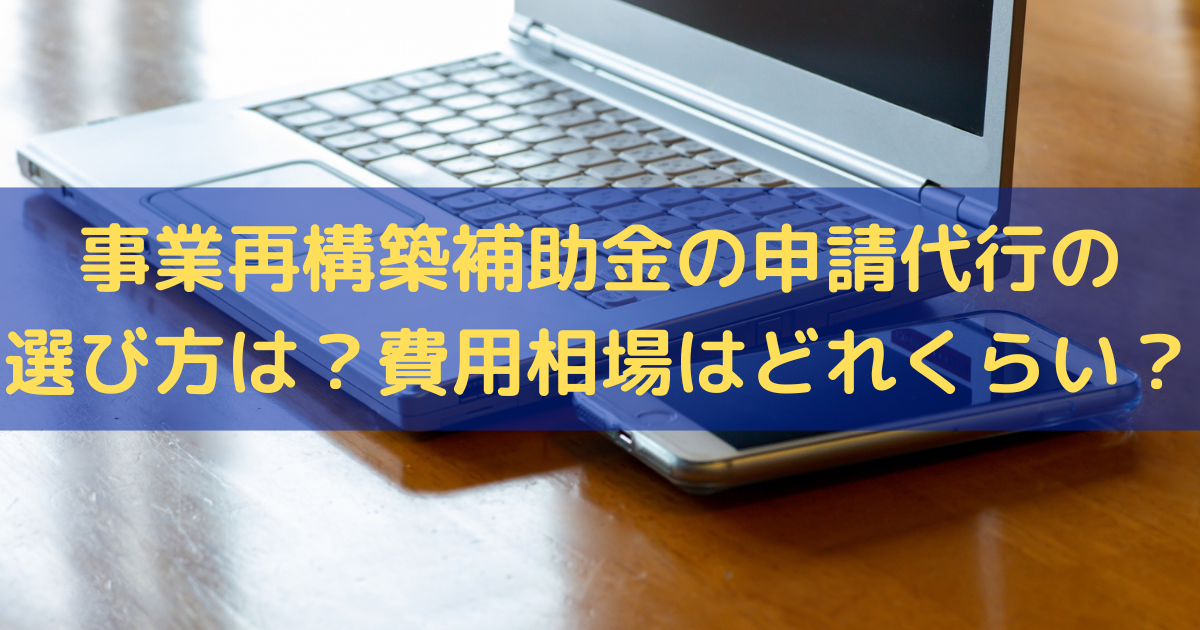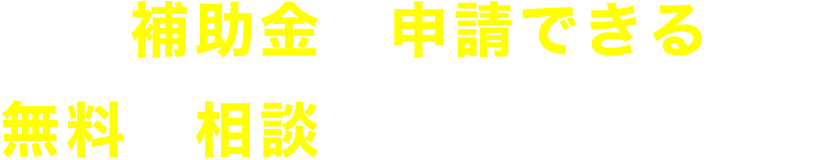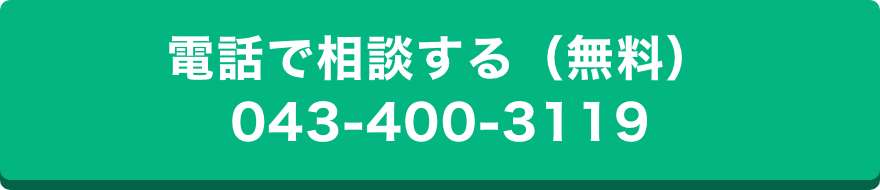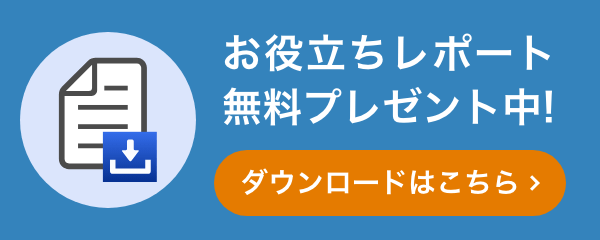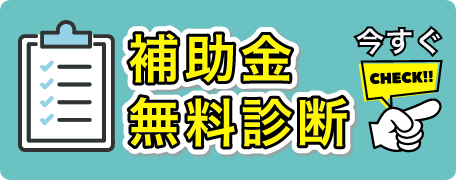※2025年4月追記:事業再構築補助金の公募は終了しております。事業再構築補助金の後継として新設された、下記の「中小企業新事業進出補助金」をチェックしてください。
2025年3月現在、事業再構築補助金の最終公募がなされています。事業再構築補助金は新型コロナ禍で誕生した非常に大型の補助金であり、補助上限額は数千万円にも上ります。しかし、2024年にはほとんど公募されておらず、2025年度には継続されないことが決まりました。
そのような中、2025年1月に突如として事業再構築補助金の最後の公募が公表されました。この最終公募の締切は2025年3月26日であるため、ご希望の事業者様は一刻も早く専門家へ相談し申請準備に取り掛かることをおすすめします。
では、事業再構築補助金の申請代行や申請サポートは誰に依頼すればよいのでしょうか?また、専門家に事業再構築補助金の申請代行を依頼した場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
今回は、事業再構築補助金の制度概要や2025年3月現在における最新情報を紹介するとともに、申請代行先の選び方や申請代行を依頼した場合の費用相場などについてくわしく解説します。事業再構築補助金に申請できる最後の機会であり申請期限も迫っているため、この機会を逃さないようご注意ください。
当社トライズコンサルティングでは事業再構築補助金の申請代行実績が豊富であり、サポートした案件について高い採択率を誇っています。最終公募の締切が迫っているため、申請をご希望の事業者様は、当社トライズコンサルティングまでできるだけ早期にご相談ください。
事業再構築補助金の概要
事業再構築補助金とは、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し当面の需要や売上の回復が期待し難い中、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とする補助金です。
次のような「思い切った事業の再構築」に要する資金が補助対象となります。
- 新市場進出(新分野展開、業態転換)
- 事業・業種転換
- 事業再編
- 国内回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化
- これらの取り組みを通じた規模の拡大等
補助金額の上限は、基本の申請枠である「成長分野進出枠(通常類型)」の場合、従業員数に応じてそれぞれ次のとおりです。
- 従業員数20人以下:1,500万円
- 従業員数21~50人:3,000万円
- 従業員数51~100人:4,000万円
- 従業員数101人以上:6,000万円
また、短期に大規模な賃上げを行う場合には、補助上限額がさらに上乗せされます。
2024年4月23日(火)に開始された第12回公募からは申請枠が一新されているため、申請をご検討の際は最新情報にご注意ください。
事業再構築補助金の採択率
事業再構築補助金の第1回公募から第11回公募までの採択結果は、次のとおりです。なお、事業再構築補助金にはさまざまな申請類型がありますが、ここでは基本の申請枠である「通常枠(第10回以降は「成長枠」)」に絞って結果をまとめています。

| 公募回 | 応募件数 (受付件数) | 採択者数 | 採択率 |
| 第11回 | 2,508 | 698 | 27.83% |
| 第10回 | 2,734 | 1,242 | 45.43% |
| 第9回 | 5,178 | 2,130 | 41.14% |
| 第8回 | 7,261 | 3,562 | 49.06% |
| 第7回 | 9,292 | 4,402 | 47.37% |
| 第6回 | 11,653 | 5,297 | 45.45% |
| 第5回 | 16,185 | 6,441 | 39.79% |
| 第4回 | 15,036 | 5,700 | 37.90% |
| 第3回 | 15,423 | 5,713 | 37.04% |
| 第2回 | 14,800 | 5,367 | 36.26% |
| 第1回 | 16,897 | 5,092 | 30.13% |
採択率は公募回を重ねるごとに徐々に上昇し、第10回前後では45%前後となっていました。しかし、第11回公募では27.83%となり、採択率が大きく落ち込んでいます。
また、12回公募までしばらく公募が止まっていたのは、内閣官房行政改革推進本部事務局が実施した「令和5年度秋の年次公開検証(「秋のレビュー」)」において、「審査の厳格化とデータの収集の厳格化については、引き続き十分な検討が必要である」などと指摘がされ、これに対応していたことにあります。そのため、今後はさらに審査が厳しくなり、低い採択率で推移する可能性があるでしょう。
事業再構築補助金は、比較的難易度の高い補助金の一つです。少しでも採択の可能性を高めるため、申請代行や申請サポートの活用をおすすめします。
事業再構築補助金でできること
事業再構築補金を活用することで、どのようなことが可能となるのでしょうか?ここでは、補助金事務局が以前公表している「活用イメージ集」を参考に、事業再構築補助金の活用イメージをまとめて紹介します。
自社の取り組みについて事業再構築補助金が活用できそうかどうかを知りたい場合は、トライズコンサルティングまでお気軽にお問い合わせください。また、新規事業を思いつかないという事業者様を対象に、新規事業コンサルティングも行っています。
宿泊施設がオートキャンプ場施設に「新分野展開」
ある事業者が宿泊施設を営んでいたものの、新型コロナの影響により収入が減少しました。これを受け、新たにオートキャンプ場施設の経営を開始するケースです。
この場合、事業再構築補助金を申請する際の事業計画では、次の3点を示すこととなります。
- 製品等の新規性要件を満たしていること
- 市場の新規性要件を満たしていること
- 3~5年の事業計画期間終了後、オートキャンプ場施設の売上高が総売上高の10%以上となること
観光バス事業者が高齢者施設向けの送迎サービスに「事業転換」
ある事業者が観光バス事業を展開していたものの、コロナ禍でインバウンド需要が低下して収入が減少しました。これを受け、既存のノウハウを活かし、新たに高齢者施設向けの送迎サービスを開始するケースです。この場合、事業再構築補助金を申請する際の事業計画では、次の3点を示すこととなります。
- 製品等の新規性要件を満たしていること
- 市場の新規性要件を満たしていること
- 3~5年の事業計画期間終了後、高齢者施設向け送迎サービスを含む事業が、売上高構成比の最も高い事業となること
宿泊業がコワーキングスペースに「業種転換」
ある事業者が宿泊業を営んでいたものの、新型コロナの影響で利用客が激減しました。これを受け、旅館の客室の大半をコワーキングスペースに改修し、新たに運営を開始するケースです。
この場合、事業再構築補助金を申請する事業計画では、次の3点を示すこととなります。
- 製品等の新規性要件を満たしていること
- 市場の新規性要件を満たしていること
- 3~5年の事業計画期間終了後、コワーキングスペースの運営を含む業種の売上高構成比が最も高くなること
イベント運営会社がライブや展示会をバーチャル上で再現するサービスに「業態転換」
ある事業者がアーティストのライブやアート展示会等の運営を担っていたものの、新型コロナウイルスの影響によりイベントの中止が続出しました。これを受け、ライブや展示会をバーチャル上で再現するサービスの提供を開始するケースです。
この場合、事業計画では次の3点を示すこととなります。
- 製品方法等の新規性要件を満たしていること
- 商品等の新規性要件または設備撤去等要件を満たしていること
- 3~5年の事業計画期間終了後、バーチャルサービスの提供による売上高が総売上高の10%以上となること
弁当屋が吸収合併で病院向けの給食などの施設給食業に「事業再編」
オフィス街で弁当屋を営んでいたものの、コロナの影響によるテレワークの増加により売上が低迷しました。
これを受け、吸収分割を行ったうえで新たに病院向けの給食などの施設給食業に着手するケースです。
この場合、事業再構築補助金を申請する際の事業計画では、次の4点を示すこととなります。
- 会社法上の組織再編行為(吸収分割)を行っていること
- 製品等の新規性要件を満たしていること
- 市場の新規性要件を満たしていること
- 3~5年の事業計画期間終了後、施設給食業の売上高が総売上高の10%以上となること
なお、新規事業を思いつかないという方は、新規事業コンサルティングをご検討ください。
2025年3月現在申請できる事業再構築補助金
2024年1月10日、事業再構築補助金の最終公募(第13回公募)が公表されました。前回の公募から半年近くが空いているため、待ち望んでいた事業者様も少なくないことでしょう。」最終公募の申請スケジュールは、次のとおりです。
| 公募開始 | 2025年1月10日(金) |
| 申請受付 | 2025年2月7日(金) |
| 応募締切 | 2025年3月26日(水)18:00 |
事業再構築補助金は廃止されることが決まっており、これが最後の公募です。申請をご希望の事業者様は申請期限に間に合わせるため、一刻も早く当社トライズコンサルティングへご相談ください。申請期限が近くなると依頼を受けられない可能性も生じるため、後悔のないよう早めの相談をおすすめします。可能性も生じるため、後悔のないようお早めの相談をおすすめします。
2025年(令和7年)3月の事業再構築補助金の概要
2025年1月に公募が開始された第13次公募における申請枠と補助上限額は、それぞれ次のとおりです。なお、それぞれのカッコ書きは、短期に大規模な賃上げを行う場合に適用される補助金額や補助率です。
| 申請枠 | 補助上限額 | 補助率 | ||
| 成長分野進出枠 | 通常類型 | 中小企業者等 | ・従業員数20人以下:100万円~1,500万円(2,000万円) ・従業員数21~50人:100万円~3,000万円(4,000万円) ・従業員数51~100人:100万円~4,000万円(5,000万円) ・従業員数101人以上:100万円~6,000万円(7,000万円) | 1/2(2/3) |
| 中堅企業等 | 1/3(1/2) | |||
| GX進出類型 | 中小企業者等 | ・従業員数20人以下:100万円~3,000万円(4,000万円) ・従業員数21~50人:100万円~5,000万円(6,000万円) ・従業員数51~100人:100万円~7,000万円(8,000万円) ・従業員数101人以上:100万円~8,000万円(1億円) | 1/2(2/3) | |
| 中堅企業等 | 100万円~1億円(1.5億円) | 1/3(1/2) | ||
| コロナ回復加速化枠 | 最低賃金類型 | 中小企業者等 | ・従業員数5人以下:100万円~500万円従業員数6~20人:100万円~1,000万円 ・従業員数21人以上:100万円~1,500万円 | 3/4 (コロナで抱えた債務の借り換えを行っていない者は2/3) |
| 中堅企業等 | 2/3 (コロナで抱えた債務の借り換えを行っていない者は1/2) | |||
| 卒業促進上乗せ措置 | 中小企業者等 | 各事業類型の補助金額上限に準じる | 1/2 | |
| 中堅企業等 | 1/3 | |||
| 中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 | 中小企業者等 | 100万円~3,000万円 | 1/2 | |
| 中堅企業等 | 1/3 | |||
自社がどの枠に申請すべきかわからない場合や、自社が申請要件を満たすかどうか知りたい場合などには、当社トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。などには、当社トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。
事業再構築補助金のスケジュール
事業再構築補助金の申請から受給までは、どのような流れとなるのでしょうか?ここでは、一般的な手続きスケジュールを紹介します。
- 申請書類を作成する
- 申請する
- 採択・不採択が通知される
- 補助対象事業を実施する
- 事業の実施報告をする
- 事業再構築補助金が交付される
申請書類を作成する
初めに、事業再構築補助金の申請書類を作成します。申請書類はいきなり書き始めるのではなく、申請内容や事業計画を十分に練り込んだうえで作成を始めることをおすすめします。
専門家に申請代行や申請サポートを依頼した際は、はこの申請書などを練り込むコンサルティングを受けられることが一般的です。
申請する
申請書類が作成できたら、公募期間内に申請します。事業再構築補助金の申請は電子申請によってのみ行うことが可能であり、事務局への持ち込みや郵送などでの申請はできません。
採択・不採択が通知される
公募期間の満了後に採択か不採択かが決まり、申請者全員へ通知されます。また、事務局の公式ホームページでも、採択案件の一覧が公表されます。
補助対象事業を実施する
事業補助金に採択されても、すぐに補助金を受け取れるわけではありません。採択後はまず交付申請を行い、その後補助対象とした事業(経費の支出など)を行うことが必要です。
補助対象事業を実施する時点ではまだ補助金は受け取れていないため、事業の実施に必要な資金を一時的な融資でまかなうことも少なくありません。
事業の実施報告をする
補助対象事業を実施したら、事務局に対して実績報告を行います。この実績報告には多くの書類が必要となるほか相当な手間もかかるため、専門家に代行やサポートを受けることをおすすめします。
事業再構築補助金が交付される
実績報告に問題がないと判断されると、補助金が交付されます。事業再構築補助金は採択から入金までには、1年から1年半程度がかかることも少なくありません。
事業再構築補助金の事業計画書作成のポイント
事業計画書の内容が、事業再構築補助金が採択されるかどうかのカギを握ると言っても過言ではありません。
では、事業再構築補助金の申請で提出する事業計画書の作成では、どのようなポイントを踏まえればよいのでしょうか?ここでは、事業計画書を作成するポイントを4つ解説します。
- 審査項目を踏まえて作成する
- 全体の整合性を確認する
- 審査員へのわかりやすさを心がける
- できるだけ早くから取り掛かる
審査項目を踏まえて作成する
事業再構築補助金は公募要領で審査項目が公表されており、補助金事務局はこの審査項目をベースとして各申請の採択・不採択を決めることとなります。そのため、審査項目を十分理解したうえで、審査項目を満たしている場合はその旨を事業計画書内でアピールするとよいでしょう。
事業計画書の作成代行をご検討の方は、こちらを参照してください。
全体の整合性を確認する
事業計画を作成したらこれで満足するのではなく、必ず全体の整合性を確認してください。事業計画の矛盾が大きい場合は事業計画の実現性に疑念が生じ、採択が遠のくリスクがあります。
事業計画を単なる机上の空論と考えるのではなく、実際に自社で行っていく取り組みであると考えれば、自ずと整合性が見えてくるはずです。たとえば、事業所を新たに開設する計画となっている場合はそこに配置する従業員が必要であり、この点も事業計画に落とし込まなければなりません。
審査員へのわかりやすさを心がける
事業計画を作成する際は、審査員への分かりやすさを心がけましょう。たとえば、自社の業界では頻繁に使用される用語であっても、その業界外部にいる審査員にとっては理解がしづらいかもしれません。
また、業界内では画期的な取り組みであったとしても、業界外の審査員にはそれがどれほど凄いことであるのかピンと来ない可能性もあります。そのため、専門用語に注釈をつけたり、業界における前提知識を丁寧に説明したりするなど、第三者が見ても理解しやすい内容の事業計画を作成することがポイントです。
できるだけ早くから取り掛かる
事業再構築補助金を申請するための事業計画書の作成は、できるだけ早くから取り掛かることをおすすめします。
よい事業計画は、一夜漬けなどで作成できるものではありません。また、時間的な余裕がないと、必要な検討が漏れやすくなります。
そのため、事業再構築補助金の申請をご検討の際は期限が迫ってから準備に取り掛かるのではなく、時間に十分余裕を持って専門家にコンタクトをとってください。期限が近くなると専門家のスケジュールが埋まってしまい、申請代行や申請サポートを依頼できない可能性も生じます。
事業再構築補助金の申請代行とは?
事業再構築補助金の申請代行とは、どのようなサポートを指すのでしょうか。
ここでは、申請代行の概要を解説します。
申請代行で依頼できること
(1)事業計画書作成支援
申請書の中心となる事業計画書の作成をサポートしてもらうことができます。事業計画書は、「補助事業の具体的取組内容」「将来の展望」「本事業で取得する主な資産」「収益計画」から構成され、A4サイズで15枚以内にまとめる必要があります(補助金額が1,500万円以下なら10枚以内)。
計画を立てるのは事業者自身ですが、事業者からのヒアリングに基づきコンサルタントが計画書をまとめます。また、コンサルタントが計画書を作成するだけでなく、事業者が作成した計画書を添削してくれるようなサービスもあります。
(2)実績報告書等の作成支援
採択後も実績報告書等の提出が必要です。このような採択後の報告書作成支援を手掛ける業者もあります。
(3)その他サポート
事業再構築補助金は、「Jグランツ」という補助金申請サイトから事業者自身が電子申請によって申請します。また、財務情報をレーダーチャートで表した「ローカルベンチマーク」資料の提出も必要になります。
いずれも入力するだけですが、パソコン操作やシステムにあまり慣れていない方にとっては、少しハードルが高いかもしれません。そんなときに、コンサルタントが入力方法等を教えてくれるなどサポートしてくれます。
費用相場
事業再構築補助金の申請代行や申請サポートを依頼した場合は、専門家報酬が必要となります。
具体的な報酬額は専門家によって異なるものの、相場はおおむね次のとおりです。
着手金
着手金とは、専門家にサポートを依頼した時点で発生する報酬です。
着手金は採択・不採択に関わらず発生するものであり、不採択であったからといって返還されるものではありません。
事業再構築補助金の場合、着手金は5万円から15万円程度であることが一般的です。
成功報酬
成功報酬とは、補助金が採択された場合に追加で発生する報酬です。
事業再構築補助金の成功報酬は、採択額の10%から20%程度が目安となります。
事業再構築補助金の申請代行を利用するメリット・デメリット
事業再構築補助金の申請代行や申請サポートを活用することには、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
主なメリットとデメリットを解説します。
メリット
事業再構築補助金の申請に申請代行や申請サポートを活用する主なメリットは、次の2点です。
手間や時間を削減できる
事業再構築補助金の申請代行や申請サポートを依頼した場合、自社でかける手間や時間を大きく削減することが可能となります。
その結果、自社の本業に注力しやすくなります。
採択の可能性を高められる
事業再構築補助金の申請代行や申請サポートを専門家へ依頼することで、採択の可能性を高めることが可能となります。
これは、専門家からコンサルティングを受けることで、事業計画の精度が高まるためです。
また、専門家が審査ポイントや加点項目を熟知したうえで書類の作成を支援してくれることも、採択へつながりやすくなる理由の1つといえます。
デメリット
事業再構築補助金の申請代行や申請サポートを活用する主なデメリットは、次の2点です。
専門家報酬がかかる
事業再構築補助金の申請代行や申請サポートを活用すると、専門家報酬がかかります。
専門家報酬の相場は、先ほど解説したとおりです。
稀に悪質な業者が混じっていることがある
事業再構築補助金の申請代行や申請サポートを行う専門家の中には、稀に悪質な業者が混じっていることがあります。
悪質な業者に依頼してしまえば粗悪な申請書類を作成され採択が遠のくおそれがあるほか、事前に説明のなかった不明瞭な報酬を請求されてトラブルとなるおそれが生じます。
また、虚偽申請をそそのかれてしまうかもしれません。
そのため、国家資格を有している専門家を選んだり事前に口コミを調べたりするなど、信頼できる専門家を選ぶようにご注意ください。
事業再構築補助金の申請代行業者の選び方
事業再構築補助金の申請代行や申請サポートを依頼する専門家は、どのように選定すればよいでしょうか?ここでは、専門家を選ぶ際の確認ポイントを3つ解説します。
- 保有する資格
- 採択実績
- サポート体制
保有する資格
1つ目は、専門家の保有資格です。
事業再構築補助金の申請代行や申請サポートは、中小企業診断士や税理士、行政書士などさまざまな事業者が行っています。その中でも、中小企業診断士は事業再構築補助金の申請にあたって重要なポイントとなる事業計画の策定や練り込みのサポートを得意としており、事業再構築補助金の申請代行や申請サポートの依頼先としておすすめです。
採択実績
2つ目は、採択実績です。
同じ資格を有していても、事業再構築補助金の申請サポートの実績や知識などは、その専門家によってさまざまです。そのため、専門家の保有資格は一つの重要な基準となるものの、それだけで申請代行先を決めるのではなく、その専門家のサポート実績などを確認したうえで依頼することをおすすめします。
サポート体制
3つ目は、サポート体制です。
たとえば、打ち合わせは毎回専門家の事務所に出向く必要があるのか、それともZoomなどのオンラインツールに対応しているかどうかなどです。
事業再構築補助金の申請を希望する事業者様は、新たな事業の立ち上げに向けて多忙を極めていることが多いでしょう。そうであるからこそ、専門家を選ぶ際は、専門家によるサポート体制も加味するようにしてください。
事業再構築補助金の申請代行ならトライズコンサルティングにお任せください!
事業再構築補助金の申請代行や申請サポートは、当社トライズコンサルティングへお任せください。トライズコンサルティングの概要と、当社にご依頼いただく主なメリットについて解説します。
トライズコンサルティングとは
トライズコンサルティングとは、中小企業診断士の資格を有する野竿が代表を務めるコンサルティング企業です。「お客さまの目標実現のため、ワクワクするような成果を提供します」をコンセプトに、補助金申請サポートや経営計画の策定などを得意としています。
トライズコンサルティングには、補助金の申請サポートを得意とする専門家が多く在籍しており、日々ご相談やサポートにあたっています。中でも、代表の野竿は、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として国が認定する「認定経営革新等支援機関」としても登録されており、確かな知識のもと、中小企業に寄り添ったサポートを実現しています。
トライズコンサルティングにご依頼頂くメリット
事業再構築補助金の申請代行(申請サポート)をトライズコンサルティングにご依頼いただく主なメリットは次の4点です。
採択の可能性を高められる
トライズコンサルティングでは、事業再構築補助金の申請サポートについて高い採択率を誇っています。当社でサポートした事業再構築補助金の申請のうち、2023年5月時点までの採択件数は80件、採択率は86.9%でした。
当社では、トップコンサルタントが申請へ向けて事業計画の練り込みを支援するほか、事業再構築補助金の制度趣旨や審査ポイントを熟知したうえで申請サポートを行うことから、高い採択率へとつながっています。
料金体系が明瞭で安心できる
トライズコンサルティングでは明瞭な料金体系を採用しており、報酬額についてご依頼前にしっかりとご案内しています。不明瞭な料金や説明していなかった料金を請求することはありませんので、安心してご依頼頂くことが可能です。
Zoomを使って全国各地から相談できる
トライズコンサルティングでは、Zoomなどを活用して打ち合わせを行っています。そのため、忙しい事業者様が時間を無駄にすることなく、補助金申請に関するご相談や打ち合わせが可能となります。
また、近隣の事業者様のみならず、日本全国どこからでもご依頼やご相談頂くことが可能です
交付申請や実績報告まで一貫してサポートが受けられる
トライズコンサルティングでは、補助金の交付申請や実績報告まで一貫したサポートが可能です。
先ほども解説したとおり、事業再構築補助金は採択されてもすぐにお金が受け取れるわけではありません。採択後はまず交付申請を行う必要があるほか、事業の実施後には実績報告も必要です。
この交付申請や実績報告にも相当な手間がかかるため、これらをすべて自社で行おうとすると、本業に割くべきリソースを圧迫する可能性があります。しかし、補助金の申請をサポートする専門家は申請までがサポート範囲であり、交付申請や実績報告には関与しないことが少なくありません。
トライズコンサルティングでは交付申請や実勢報告についてもサポートを行うため、事業者様は、自社の本業に注力しやすくなります。
事業再構築補助金に関するよくある質問
最後に、事業再構築補助金に関するよくある質問に3つ回答します。
既に事業再構築を行って自社で支出した費用は補助対象となる?
申請前に支出した費用は補助対象とはなりません。事業再構築補助金の対象となる経費は、申請をして採択を受け、さらに交付申請を行い、交付決定を受けた後に支出したもののみです。
ただし、一定の手続きを踏んで事務局から承認された場合には、交付決定前に支出した経費であっても補助対象とできる場合があります。とはいえ、申請前に支出した経費までさかのぼって補助対象とできるわけではありません。
採択のためには早く申請した方が有利になる?
申請のタイミングが早かったからといって、採択において有利となることはありません。むしろ、焦って申請をすると申請内容の練り込みが足りず、採択が遠のくリスクがあります。
採択の可能性を高めるためには、早めに専門家へコンタクトをとり、事業計画などの申請内容をブラッシュアップする時間を十分に確保することをおすすめします。
他の補助事業との併用は可能?
結論をお伝えすると、同一の事業について複数の補助金を受給することはできません。ただし、同一の企業であっても対象とする事業が異なるのであれば、複数の補助金を併用することが可能です。
自社のケースで補助金が併用できるかどうか知りたい場合は、専門家へご相談ください。
まとめ
事業再構築補助金の概要や2025年3月時点における最新情報を紹介するとともに、専門家による申請代行を活用するメリットや注意点、事業再構築補助金の申請代行先を選ぶポイントなどを解説しました。
事業再構築補助金は新型コロナ禍で誕生した非常に大型の補助金であり、多くの事業者が活用してきました。しかし、2024年12月に公表された「令和6年補正予算案」により廃止が決まっており、2025年度には後継となる「新事業進出補助金」が公募される予定です。
公募が再開されないまま廃止されると思われていた事業再構築補助金ですが、2025年1月に急遽、最後の公募が開始されました。この最終公募(第13回公募)の締切は、2025年3月26日です。
事業再構築補助金への申請をご希望の事業者様は最終公募に間に合うよう、一刻も早く申請代行・申請サポートを行っている専門家へご相談ください。
当社トライズコンサルティングは事業再構築補助金の申請代行について豊富な実績を有しており、サポートした案件で高い採択率を誇っています。事業再構築補助金の最終公募への申請後ご希望の事業者様は、当社トライズコンサルティングまでできるだけ早期にご相談ください。
事業再構築補助金の活用に関するご相談は、初回無料です。また、Zoomなどのオンラインツールを活用しているため、近隣の事業者様のみならず、全国どこからでもご相談・ご依頼いただけます。