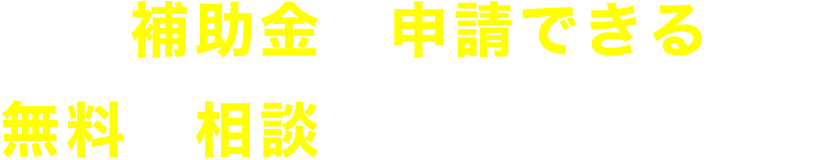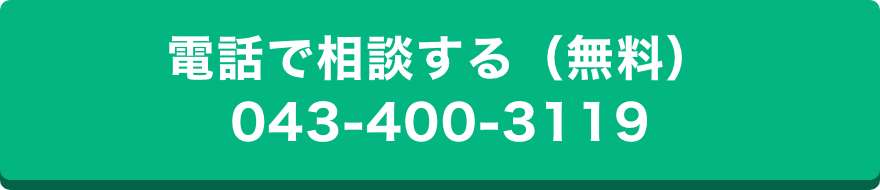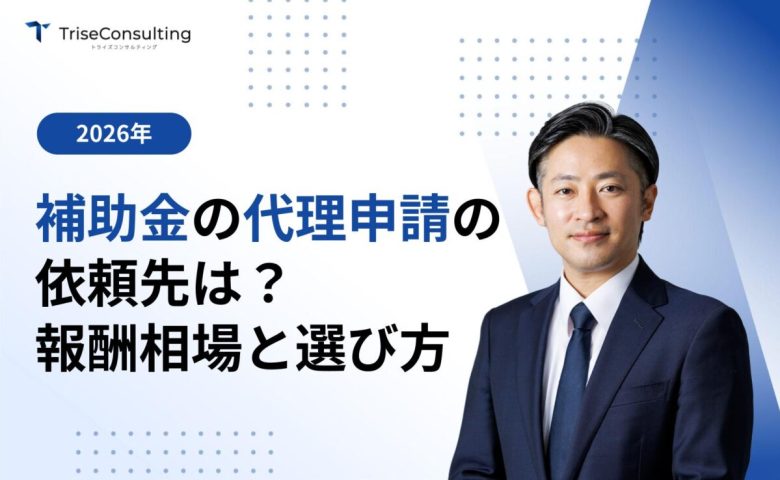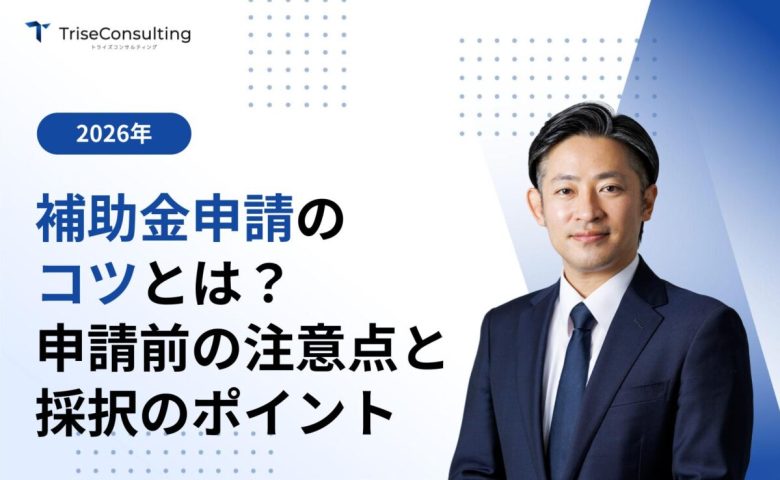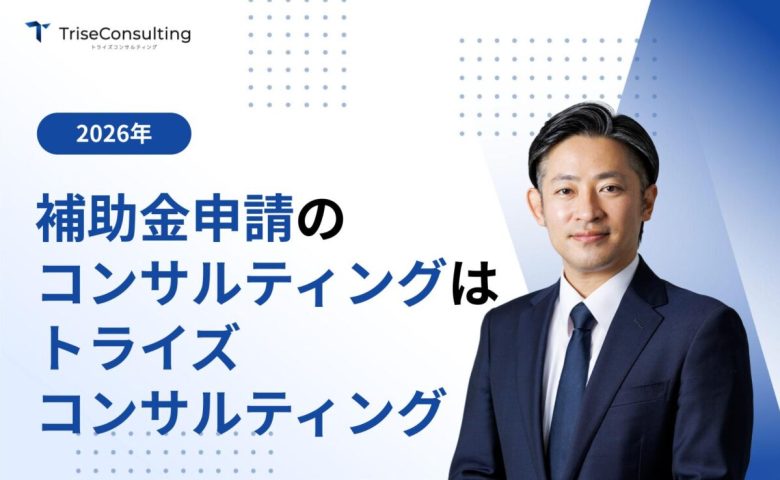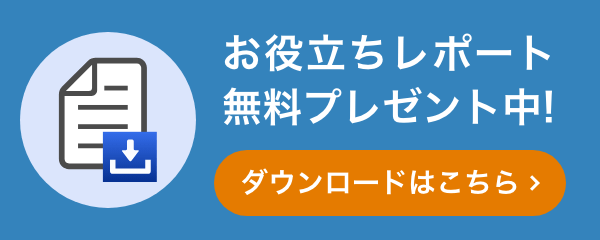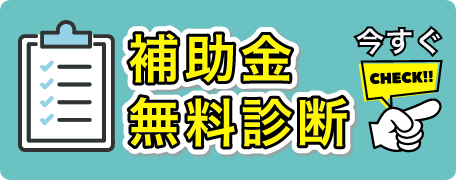「経営力向上計画」とは、企業が独自に策定する経営力を向上させるための計画です。この計画について申請し、認定を受けることで、企業は税制優遇措置などさまざまなメリットが享受できます。また、コンサルタントのサポートを受けて経営力向上計画を練り込むこと自体が、自社の経営力の飛躍的な向上につながるでしょう。経営力向上計画の策定により自社の成長を目指したい事業者様や優遇措置の適用を受けたい事業者様は、計画の策定や申請にチャレンジすることをおすすめします。
しかし、経営力向上計画の策定や承認申請を進めようにも、何から手を付ければよいかわからない事業者様も多いと思います。そのため、経営力向上計画の策定に興味がある際はまず専門家へ相談し、専門家のサポートを受けて行うとよいでしょう。
では、経営力向上計画の認定とはどのような制度であり、認定を受けることでどのようなメリットを享受できるのでしょうか?また、経営力向上計画の策定サポートや申請代行は、誰に依頼すればよいのでしょうか?今回は、経営力向上計画の概要や認定を受けた場合に享受できるメリットをまとめて紹介するとともに、専門家による申請代行を活用するメリットや専門家の選び方などについてくわしく解説します。
なお、当社トライズコンサルティングは経営力向上計画の策定支援や認定申請のサポートについて豊富な実績を有しています。トライズコンサルティングとは、中小企業診断士であり認定支援機関でもある野竿が代表を務めるコンサルティング企業です。経営力向上計画の策定や認定申請に関心のある事業者様は、当社までお気軽にご相談ください。
目次
Toggle経営力向上計画とは
経営力向上計画とは、人材育成やコスト管理などのマネジメントの向上や設備投資など、企業が自社の経営力を向上するために策定・実施する計画です。公式ホームページによると、次の内容などを示す計画が想定されています。
- 企業の概要
- 現状認識
- 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
- 経営力向上の内容
- (事業承継等を行う場合)事業承継等の時期と内容
計画は自社だけで策定するのではなく、「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」の支援を受けることでより効果的な計画策定が可能となります。認定支援機関とは中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として国の認定を受けた支援機関であり、当社トライズコンサルティングの代表である野竿も登録を受けています。
経営力向上計画は、策定をするだけでも自社の経営が「見える化」でき理想とのギャップが具体的に把握できることから、自社の飛躍に役立つものです。しかし、経営革新計画には認定制度が設けられており、認定を受けることで税制優遇措置などさらなる優遇措置の対象となります。
優遇措置の内容は次でくわしく解説するものの、計画実現のために導入した設備について税制優遇が受けられるなど、いずれも計画の実現を制度面から支援する内容となっています。経営力向上計画を策定する際は、ぜひ認定を受けることまでを目指すとよいでしょう。経営力向上計画の策定や認定申請でお困りの際は、当社トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。初回のご相談は、無料です。
経営力向上計画を申請し認定を受ける主なメリット
経営力向上計画を申請して認定を受けた場合、どのようなメリットが享受できるのでしょうか?ここでは、認定を受けた場合に適用対象となる主な優遇措置について概要を解説します。
- 税制優遇措置の対象となる
- 補助金申請時の加点対象となる
- 金融支援の対象となる
- 法的支援の対象となる
税制優遇措置の対象となる
経営力向上計画の認定を受けた場合、認定計画に基づいて取得した一定の設備や不動産について、法人税や不動産取得税などの特例措置の対象となります。
具体的には、次の措置などが挙げられます。
- 中小企業経営強化税制:法人税(個人事業主は、所得税)について、即時償却または取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は、7%)の税額控除が選択適用できる
- 事業承継等に係る不動産取得税の特例:他者から事業を承継するために土地・建物を取得する場合、不動産取得税の軽減措置の適用対象となる
- 中小企業事業再編投資損失準備金:経営力向上計画に基づいて株式等を取得し、これを事業年度末まで引き続き有している場合に、株式等の取得価額として計上する金額の一定割合を準備金として積み立てたときは、その積立金を損金算入できる
なお、税制優遇措置を受けるには「資本金1億円以下であること」など、他のさまざまな要件を満たさなければなりません。税制優遇を目的として経営力向上計画の認定をご検討の際は、あらかじめ適用を受けたい優遇措置の要件をご確認ください。
補助金申請時の加点対象となる
経営力向上計画の認定を受けた場合、一定の補助金の審査において加点の対象となります。
補助金とは、要件を満たして期限内に申請することで、国などから返済不要な事業資金を受け取れる制度です。中には数千万円や数億円を受け取れる補助金もあり、うまく活用することで事業の成長スピードを格段に早めることが可能となるでしょう。
しかし、補助金は申請したからといって必ずしも受け取れるものではなく、多数の申請の中から補助対象に相応しいとして選ばれる(採択される)必要があります。
採択事業者を決めるにあたっては、多くの補助金で、一定の要件を満たした場合に加点される仕組みが採られています。加点対象は補助金の制度によって異なるものの、経営力向上計画の認定を受けていることが加点対象となる補助金は少なくありません。
金融支援の対象となる
経営力向上計画の認定を受けた場合、金融支援措置の対象となります。たとえば、政策金融機関の融資や民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証などの資金調達に関する支援などを受けることが可能です。
金融支援を目的として経営力向上計画を受けようとする場合には、あらかじめ融資についてもくわしい中小企業診断士などの専門家に相談したうえで、融資の具体的な申込先などを選定することから始めるとよいでしょう。
法的支援の対象となる
経営力向上計画の認定を受けた場合、業法上の許認可の承継の特例や組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置などの法的措置の対象となります。
実際に適用を受けようとする際は、適用を受けたい法的支援の内容に応じて、行政書士や司法書士、弁護士などの専門家へ相談するとよいでしょう。
経営力向上計画を申請できる事業者の範囲
経営力向上計画を申請できる事業者は、「特定事業者等」に該当する事業者です。特定事業者等とは、原則として従業員数2,000人以下の次の者です。
- 個人事業主
- 会社(有限会社を含む会社法上の会社・士業法人)
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
- 一般社団法人
- 医業を主たる事業とする法人
- 歯科医業を主たる事業とする法人
- 社会福祉法人
- 特定非営利活動法人
ただし、個人事業主の場合は開業届が提出されていなければなりません。また、2~9の法人は法人設立登記がされている必要があります。
なお、ここで紹介した「経営力向上計画の申請ができる事業者」と、各優遇措置の対象となる事業者は必ずしもイコールではありません。規模などによっては「経営力向上計画の認定」が可能な一方で税制優遇など一部の優遇措置の対象からは外れる可能性があるため、この点について誤解のないようご注意ください。
経営力向上計画を申請する流れ
経営力向上計画の認定を受けたい場合、どのような流れで申請を進めればよいのでしょうか?ここでは、一般的な流れについて解説します。
- コンサルタントに相談する
- 事前確認と準備をする
- 経営力向上計画を策定する
- 経営力向上計画を申請する
- 経営力向上計画を実施する
コンサルタントに相談する
経営力向上計画の申請は無理に自社だけで行わず、コンサルタントによる計画策定支援や申請サポートを依頼するとスムーズです。そのため、まずは経営力向上計画の申請サポートなどに力を入れている専門家にコンタクトをとるとよいでしょう。
経営力向上計画の申請サポート・策定支援を依頼できる専門家については、後ほどくわしく解説します。
事前確認と準備をする
次に、経営力向上計画の認定を受ける目的である制度について、事前確認と準備を行います。
先ほど解説したように、経営力向上計画の認定を受けられる要件と各優遇制度の適用を受けられる要件は、同じではありません。そのため、あらかじめ適用を受けたい優遇措置について要件などを確認しておくべきでしょう。確認や準備をすべき事項は次のとおりです。
参照元:– 中小企業等経営強化法 – 経営力向上計画策定の手引き(中小企業庁)
税制措置を受けたい場合
税制優遇措置を受けたい場合における主な確認・準備事項は、次のとおりです。
- 適用対象者の要件(資本金1億円以下など)の確認
- 具体的な適用手続きの確認
- 設備投資について税制措置を受けるためには、計画申請時に「工業会証明書」や「経産局確認書」などが必要となるため、これらの手配
- 事業承継等に伴う準備金の積立や不動産取得税の軽減については、対象となる事業承継等の条件と手続きの確認
金融支援を受けたい場合
金融支援を受けたい場合における主な確認・準備事項は、次のとおりです。
- 適用対象者の要件と手続きの確認
- 必要に応じ、関係機関への相談(金融支援を受けるには、計画申請前に関係機関への相談が必要)
法的支援を受けたい場合
法的支援を受けたい場合における主な確認・準備事項は、次のとおりです。
- 承継が認められる許認可の種類や条件の確認
- 必要な手続きの確認
- 所管行政庁への事前相談
経営力向上計画を策定する
続けて、専門家からコンサルティングを受けて経営力向上計画を策定します。「事業分野別指針」が策定されている業種では、この指針を踏まえて計画を策定しなければなりません。
指針が設けられている主な業種は、2025年1月時点で次のとおりです。
- 製造業
- 卸・小売業
- 外食・中食
- 旅館業
- 医療
- 保育
- 介護
- 障害福祉
- 貨物自動車運送業
- 船舶産業
- 自動車整備
- 建設業
- 有線テレビジョン放送業
- 電気通信
- 不動産業
- 地上基幹放送分野
- 石油卸売業・燃料小売業
- 旅客自動車運送事業
- 職業紹介事業・労働者派遣事業分野
- 学習塾業分野
- 農業分野
経営力向上計画は認定を受けるためだけに策定するものではなく、今後実際に経営を向上させていく際の拠りどころとなるものです。認定を受けるための申請をきっかけとして計画を練り込むことで、今後の経営を向上させるにあたって心強い羅針盤となるでしょう。
経営力向上計画を申請する
経営力向上計画が策定できたら、これを各事業分野の主務大臣に申請します。
なお、電子申請の場合には「経営力向上計画申請プラットフォーム」からの申請ができるものの、一部の省庁宛ての申請や都道府県経由が必要な申請など、一部の申請は電子申請に対応していません。そのため、自社の申請先を確認したうえで、申請方法も確認しておきましょう。
経営力向上計画を実施する
無事に認定が受けられた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請書の写しが交付されます。
申請から認定までに要する期間の目安は、休日を除いて原則30日間(複数省庁にまたがる場合の目安は45日。経営力向上計画申請プラットフォームによる電子申請かつ経済産業部局宛てのみの申請である場合の目安は14日)です。
経営力向上計画が認定されたら、税制措置や金融支援、法的支援を受けて、経営力向上のための取り組みを実行します。
経営力向上計画の申請でコンサルタントのサポートを受けるメリット
経営力向上計画の申請にあたって専門家からコンサルティングやサポートを受けることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?ここでは、専門家による申請サポートを活用する主なメリットを3つ解説します。
- 客観的な視点で経営計画の確認が受けられる
- 計画のブラッシュアップが可能となる
- 経営力向上計画を最大限活用しやすくなる
客観的な視点で経営計画の確認が受けられる
1つ目は、客観的な視点で経営力向上計画の確認が受けられることです。
自社だけで経営計画を策定した場合、客観的な視点を持つことは容易ではないでしょう。そのため、問題のない計画が策定できたと考えても、実際には自社の強みや弱みが正確に把握できていなかったり、重要な視点が漏れていたりすることは少なくありません。
外部のコンサルタントに経営力向上計画の策定支援を受けることで、客観的な視点を入れることが可能となり、より実効性の高い効果的な計画が策定しやすくなります。このように策定した計画は、実際に計画を実現していく際の羅針盤となるでしょう。
計画のブラッシュアップが可能となる
2つ目は、計画のブラッシュアップが可能となることです。
専門家にサポートを受けることで、経営力向上計画のブラッシュアップが可能となります。その結果、全体の整合性が取れた実現性の高い計画策定につながるでしょう。
また、一部業種では「事業分野別指針」に沿った計画策定が必要ですが、専門家のサポートを受けることでこれを踏まえた策定もしやすくなります。
経営力向上計画を最大限活用しやすくなる
3つ目は、経営力向上計画を受けるメリットを最大限享受しやすくなることです。
経営力向上計画の申請を希望する場合、「税制優遇措置を受けるため」など具体的なメリットの享受が目的となることが多いです。その一方で、当初目的とした以外の優遇措置を理解しておらず、メリットを十分に享受できない場合も少なくないようです。
経営力向上計画の申請にあたって専門家にサポートを受けることで、他の優遇措置についてもアドバイスが受けられるため、経営力向上計画の認定を受けるメリットを最大限に享受しやすくなります。
経営力向上計画の申請代行は誰に依頼すれば良い?
経営力向上計画の策定支援や申請サポートは、誰に依頼すればよいのでしょうか?ここでは、依頼先の主な選択肢について解説します。
- 中小企業診断士
- 税理士
- 行政書士
- 民間コンサルタント
中小企業診断士
中小企業診断士は、中小企業の経営診断や経営コンサルティングを専門とする国家資格です。経営計画の策定を得意としているため、経営力向上計画の申請サポートの依頼先として適任だといえます。
中小企業診断士にサポートを依頼することで、自社の経営を向上させる効果的な経営計画が策定しやすくなります。
税理士
税理士は、言わずと知れた税務の専門家です。
経営計画も税務と同じ「数字」を扱う点で、税理士が経営計画の策定に強いと考えている場合もあるでしょう。しかし、税務と経営計画とは、似て非なるものです。
そのため、経営力向上計画の申請サポートを受けている税理士がいる一方で、取り扱っていない税理士も少なくありません。また、経営力向上計画の申請サポートを行っている場合であっても、顧問先企業に限定していることが少なくありません。
行政書士
行政書士は、官公署に提出する書類や権利義務関係の書類作成を専門とする国家資格です。
経営力向上計画の申請は許認可の承継にかかわる場合があることから、経営力向上計画の申請サポートを手がける行政書士もいます。しかし、行政書士の業務分野は非常に広く、経営力向上計画の申請サポートなどを行わない事務所も少なくありません。
行政書士へ依頼する場合には、その事務所が経営力向上計画の申請サポートを取り扱っているか否かあらかじめ確認する必要があるでしょう。
民間コンサルタント
国家資格を有していない民間のコンサルタントが、経営力向上計画の申請サポートを行っている場合もあります。信頼できる民間のコンサルタントに心当たりがある場合には、選択肢の一つとなるでしょう。
ただし、民間のコンサルタントは玉石混淆であり、非常に優秀な専門家が存在する一方で、悪質な業者も存在します。そのため、特に民間コンサルタントに経営力向上計画の申請サポートを依頼しようとする際には、そのコンサルタントの実績をあらかじめ確認することをおすすめします。
経営力向上計画の申請代行はトライズコンサルティングにお任せください
経営力向上計画の申請サポートや、当社トライズコンサルティングへお任せください。最後に、トライズコンサルティングの主な特長を5つ紹介します。
- 中小企業施策に力を入れている
- トップコンサルタントが直接サポートする
- 代表は中小企業診断士である
- 補助金や融資についても相談できる
- オンライン相談が可能である
中小企業施策に力を入れている
トライズコンサルティングは中小企業施策に力を入れており、経営力向上計画の申請サポートについても多くの実績があります。そのため、安心してお任せいただくことが可能です。
トップコンサルタントが直接サポートする
トライズコンサルティングへ経営力向上計画の申請サポートをご依頼いただいた場合、計画を策定するコンサルティング段階からトップコンサルタントが直接サポートします。そのため、自社の経営力向上に寄与する実効性の高い計画策定が可能となり、策定した計画は実際に経営を進めるうえでの重要な羅針盤となるでしょう。
代表は中小企業診断士である
トライズコンサルティングの代表である野竿は中小企業診断士であるほか、「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」としても登録されています。
認定支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関です。すべての中小企業診断士が認定支援機関であるわけではなく、中小企業診断士や税理士などのうち、実務経験が一定レベルとされた者だけが認定を受けられます。
そのため、確かな知識と実績のもと、クライアント様の経営力向上へ向けたサポートを行います。
補助金や融資についても相談できる
トライズコンサルティングは経営力向上計画の申請サポートのほか、補助金の申請サポートや融資のコンサルティングも得意としています。そのため、経営力向上計画の認定と併せて、補助金や融資についても一貫したサポートが可能です。
オンライン相談が可能である
トライズコンサルティングはZoomなどを活用したオンラインでのご相談や打ち合わせに対応しています。
そのため、近隣の事業者様はもちろん、全国どこからでもご相談・ご依頼いただくことが可能です。また、出張中先などからでも打ち合わせを進められるため、忙しい事業者様などからご好評をいただいております。
経営力向上計画の申請代行の流れ
経営力向上計画の申請は、どのような流れで進めればよいのでしょうか。ここでは、専門家に申請代行を依頼して経営力向上計画を申請する際の一般的な流れを紹介します。
- 専門家へ相談する
- 目的に応じて事前確認や準備をする
- 経営力向上計画を策定する
- 経営力向上計画を申請する
- 経営力向上計画の認定を受ける
- 計画を実行する
専門家へ相談する
経営力向上計画の申請をご希望の際は、まず専門家に相談することをおすすめします。まず専門家に相談することで経営力向上計画についての理解力が高まるほか、自社が受けられる具体的なメリットが把握でき、申請するか否かを判断しやすくなります。
目的に応じて事前確認や準備をする
専門家に相談をして経営力向上計画に申請することが決まったら、専門家のサポートや助言を受けつつ、目的(享受したいメリット)に応じて必要な事前確認や準備を行います。主な事前確認と準備は、それぞれ次のとおりです。
- 税制措置を受けたい場合:適用対象者の要件や手続きを確認する。設備投資について税制措置を受けたい場合は、工業会証明書や経産局確認書等を入手する
- 法的支援を受けたい場合:承継が認められる許認可の種類や、その他の特例の条件、必要な手続きを確認する。許認可承継の特例を受ける場合は、所管行政庁に事前相談をする
- 金融支援を受けたい場合:適用対象者の要件や手続き等を確認する。関係機関に事前相談をする
経営力向上計画を策定する
事前準備が済んだら、経営力向上計画を策定します。経営力向上計画は、まず「日本標準産業分類」で該当する事業分野を確認したうえで、その事業分野に対応する事業分野別指針を確認したうえで策定しなければなりません。
策定にあたって専門家からコンサルティングを受けることで、自社の経営力向上により寄与する計画の策定が可能となります。計画は「机上の空論」ではなく、その後実際に実行することを前提に作成しましょう。
経営力向上計画を申請する
経営力向上計画が策定できたら、認定を受けるための申請をします。申請先は各事業分野の主務大臣です。ただし、不動産取得税の軽減措置を受ける場合は都道府県経由で提出することとされています。
経営力向上計画の認定を受ける
経営力向上計画について認定が受けられた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請書の写しが交付されます。
申請から認定までにかかる期間は、休日を除き、それぞれ次の日数が目安とされています。ただし、不動産取得税の軽減措置や許認可承継の特例を利用される場合は、次の日数に加えて、関係行政機関における評価や判断にも日数が必要となります。
- 所管する省庁が単一である場合:約30日
- 複数省庁にまたがる場合:約45日
- 経営力向上計画申請プラットフォームによる電子申請かつ経済産業部局宛てのみの申請である場合:約14日
計画を実行する
経営力向上計画は認定を受けることがゴールではなく、その後その計画を実行してこそ意味を成すものです。そのため、認定を受けたら、その後は実際に計画を実行していきましょう。中小企業診断士などのコンサルタントから継続的なサポートを受けることで計画と実態の差異などの把握が可能となり、自社を飛躍させることにつながります。
まとめ
経営力向上計画の概要や認定を受けることで享受できるメリットを紹介するとともに、経営力向上計画の申請にあたって申請代行を活用するメリットや主な依頼先などについて解説しました。
経営力向上計画とは、企業が人材育成やコスト管理などのマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力向上のために策定・実施する計画です。計画を策定するだけでも目標の明確化などの効果があるものの、策定した計画について認定を受けることで、その計画を実現するためのさまざまな支援策の対象となります。代表的なものは、税制優遇措置や金融支援、法的支援などです。
経営力向上計画の認定に関心がある場合には、まずは経営力向上計画にくわしい専門家へ相談するとよいでしょう。専門家へ相談することで、自社が経営力向上計画の認定を受けることで自社が享受できる具体的なメリットが把握できます。また、専門家のコンサルティングを受けることで、より自社を飛躍させる計画の策定が可能となるでしょう。
当社トライズコンサルティングの代表である野竿は中小企業診断士であるほか認定支援機関としても登録されており、中小企業の経営力を向上させる支援について豊富な実績を有しています。経営力向上計画の申請をご検討の際や、補助金申請や融資コンサルティングなどを含めた総合的なサポートをご希望の際には、トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。
経営力向上計画に関する初回のご相談は、無料です。また、Zoomなどのオンラインツールを活用するため近隣の事業者様はもちろんのこと、全国どこからでもご相談・ご依頼いただけます。