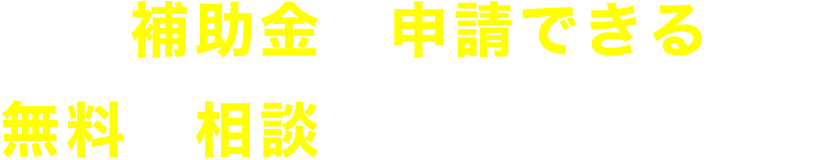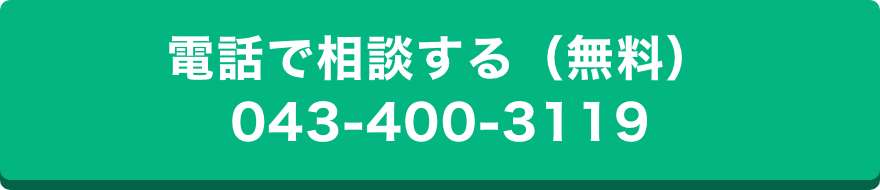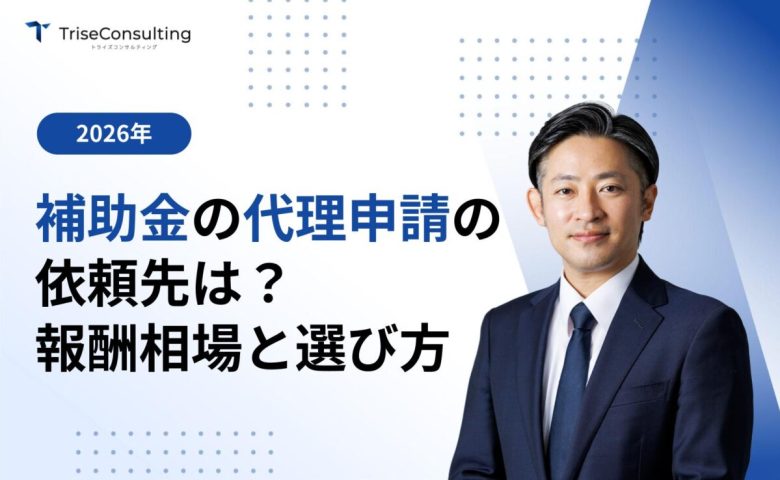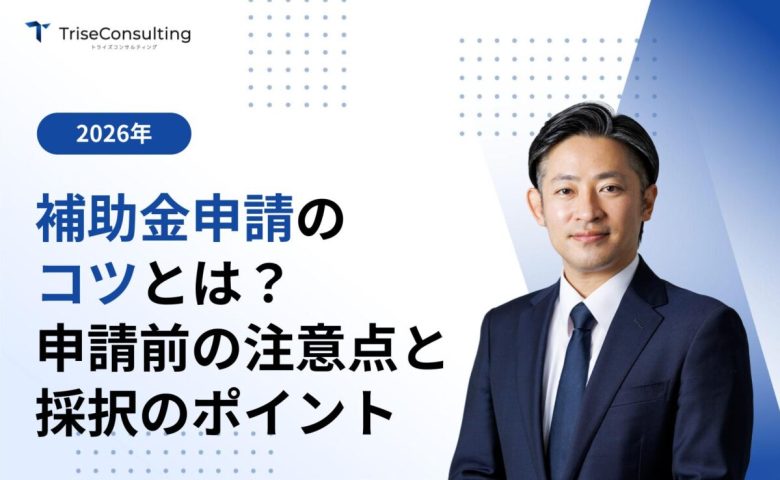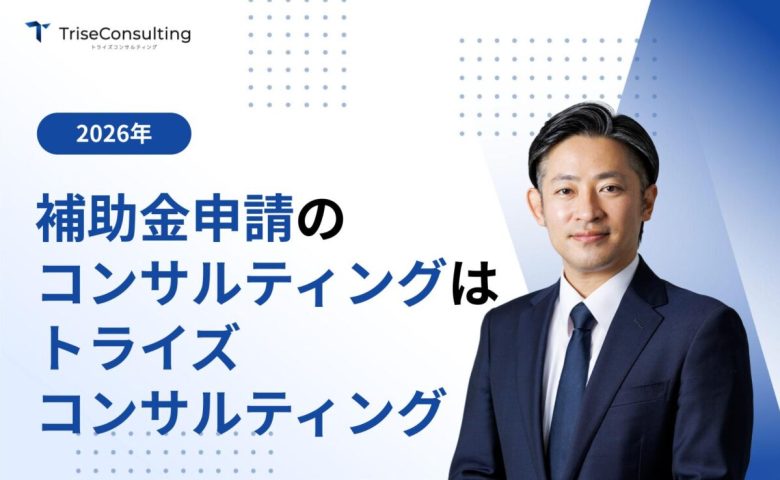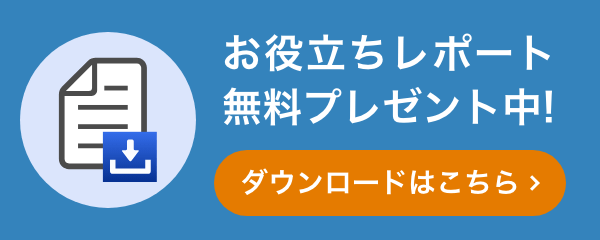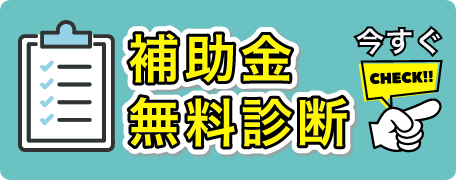小規模事業者等持続化補助金にはさまざまな申請類型が設けられており、そのうちの1つに「共同・協業型」があります。これは、小規模事業者等持続化補助金において支援対象とされる小規模事業者等自体ではなく、小規模事業者等を支援する地域振興等機関を支援する類型です。
では、小規模事業者等持続化補助金の「共同・協業型」の補助対象者や補助上限額は、どのように設定されているのでしょうか?また、「共同・協業型」への申請は、どのような手順で進めればよいのでしょうか?今回は、小規模事業者等持続化補助金の「共同・協業型」の概要や活用の流れ、申請時の注意点などについてくわしく解説します。
なお、当社トライズコンサルティングは小規模事業者等持続化補助金の申請サポート実績が豊富であり、やや特殊な類型である「共同・協業型」にも対応しています。トライズコンサルティングは、中小企業診断士である野竿が代表を務めるコンサルティング会社です。小規模事業者等持続化補助金の「共同・協業型」への申請をご希望の際は、当社までお気軽にご相談ください。
目次
Toggle小規模事業者持続化補助金の「共同協業型」とは
小規模事業者等持続化補助金の「共同・協業型」とは、地域振興等機関が実施する参画事業者の持続的な支援に要する経費の一部を補助する類型です。
地域振興等機関とは、商工会や商工会議所、商店街等の組織、地域の企業の販路開拓につながる支援を事業として行っている法人などを指します。また、地域振興等機関による支援対象である「参画事業者」とは、地域経済を支える小規模事業者を指します。
つまり、「共同・協業型」は小規模事業者そのものを補助対象とするのではなく、小規模事業者を支援する立場にある地域振興等機関を補助対象とすることで、間接的に小規模事業者を支援する類型です。これにより、地域の雇用や産業を支える参画事業者の中長期的な商品展開力・販売力の向上を図ることが目的とされています。
小規模事業者持続化補助金の共同協業型の補助対象
続いて、小規模事業者等持続化補助金の「共同・協業型」の補助対象者と、補助対象となる取り組みを解説します。自社が補助対象となるか否か判断に迷う場合には、当社トライズコンサルティングへご相談ください。
補助対象者
共同・協業型の補助対象者は、「地域振興等機関」です。地域振興等機関とは、地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関のうち、次のいずれかに該当する機関を指します。
- 商工会法・商工会議所法に基づいて設立された法人
- 中小企業等協同組合法に規定する都道府県中小企業団体中央会
- 商店街等組織(商店街その他の商業・サービス業の集積を構成する団体であって、商店街振興組合法に規定する商店街振興組合、商店街振興組合連合会及び中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合などの法人化されている組織をいう)
- 地域の企業の販路開拓につながる支援を事業として行っている法人
商工会や商工会議所などだけではなく、地域の企業の販路開拓につながる支援を事業として行っているのであれば、株式会社などの法人であっても対象となり得ます。
補助対象となる取り組み
共同・協業型の補助対象となるのは、次の要件をすべて満たす取り組みです。
- 事業効果の広がりが期待できる取り組みであること:補助事業を通じて10者以上の参画事業者を支援することで参画事業者の商品開発力・販売力の向上に繋がり、事業効果の広がる取り組みであること。また、支援の効果を補助事業終了後も把握できる取り組みであること
- 継続可能な取り組みであること:支援先の参画事業者自らがノウハウを習得し、新たな販路・取引先の獲得、売上高の増加、生産性向上等を図れるように継続的な支援が可能な取り組み(支援体制)であること。補助事業終了後も、地域振興等機関によるフォローアップによって参画事業者が継続して販路開拓できる取り組み(支援体制)であること
- ワンストップの取組であること:販路開拓の場の提供のみならず、参画事業者の商品・製品・サービスのデザイン改良やブランディング支援、生産・供給体制の向上支援、販路開拓先との取引に係る諸手続等の支援、フォローアップ等までがワンストップとなった取り組みであること
このように、地域振興等機関自身が収益を上げるための取り組みではなく、参画事業者の売上増加や販路開拓などに寄与する取り組みである必要があります。
補助対象経費
共同・協業型の補助対象となる経費は、次のとおりです。
- 人件費
- 委員等謝金
- 地域振興等機関旅費
- 参画事業者旅費
- 会議費
- 借料
- 設営・設計費(内外装費、整備工事等を含む)
- 展示会等出展費
- 保険料
- 消耗品・備品費
- 通信運搬費
- 広報費
- 印刷製本費(資料作成費を含む)
- 雑役務費
- 委託・外注費
- 水道光熱費
機会装置費などではなく、参画企業の支援に必要となる人件費や謝金などが主な補助対象とされています。なお、共同・協業型は、対象経費の分類によって補助率が異なります。補助上限額と補助率については、次で改めて解説します。
小規模事業者持続化補助金の共同協業型の補助上限額
小規模事業者等持続化補助金の共同・協業型の補助上限額は、1申請者・1公募回あたり5,000万円です。補助率は、それぞれ次のとおりとされています。
| 経費区分 | 補助率 |
|---|---|
| 人件費 | 定額 |
| 委員等謝金 | |
| 地域振興等機関旅費 | |
| 会議費 | |
| 消耗品・備品費 | |
| 通信運搬費 | |
| 印刷製本費(資料作成費を含む) | |
| 雑役務費 | |
| 委託・外注費 | |
| 水道光熱費 | |
| 参画事業者旅費 | 2/3以内 |
| 借料 | |
| 設営・設計費(内外装費、整備工事等を含む) | |
| 展示会等出展費 | |
| 保険料 | |
| 広報費 |
補助率が一律ではなく算定なども複雑となりやすいため、お困りの際は当社トライズコンサルティングまでご相談ください。当社は地域振興等機関を対象とする補助金についても対応実績を有しており、安心してお任せいただけます。
小規模事業者持続化補助金の共同協業型以外の主な申請枠
小規模事業者等持続化補助金には、共同・協業型以外にもさまざまな申請類型が設けられています。ここでは、その他の申請類型について概要を解説します。
一般型通常枠
一般型通常枠は、小規模事業者等持続化補助金のメインとなる申請類型です。小規模事業者等が行う販路開拓などの取り組みを支援するため、最大50万円を補助することとしています。補助率は、2/3です。
なお、一定の要件を満たし「インボイス特例」の適用を受けた場合には補助上限額が50万円上乗せされます。同様に、「賃金引上げ特例」の適用を受けた場合には、補助上限額が150万円上乗せされます。また、一定の赤字事業者が「賃金引上げ特例」の適用を受けた場合には補助率も3/4となり、さらなる優遇が受けられます。
地域振興等機関ではなく、小規模事業者自身が小規模事業者等持続化補助金の受給を目指す場合には、まずはこの類型への申請を目指すと良いでしょう。
一般型災害支援枠
一般型災害支援枠とは、「令和6年能登半島地震」または「2024年9月21日から23日の能登
豪雨」によって被害を受けた小規模事業者等を対象とする類型です。補助上限額は、直接被害の場合は200万円、間接被害の場合は100万円とされています。補助率は原則として2/3であるものの、一定の場合には定額となります。
創業型
創業型とは、創業後3年以内の小規模事業者を重点的に支援する申請類型です。補助上限額は200万円であり、一般型通常枠よりも優遇されています。また、「インボイス特例」の適用を受けた場合には、補助上限額が50万円引き上げられます。補助率は、一律2/3です。
ビジネスコミュニティ型
ビジネスコミュニティ型は、地域の若手経営者等や女性経営者等のグループによる取り組みにかかる経費の一部を補助する類型です。補助上限額は定額で50万円であるものの、2以上の補助事業者が共同で実施する場合は100万円となります。
小規模事業者持続化補助金の共同協業型に申請する際の注意点
小規模事業者持続化補助金の共同・協業型に申請する場合、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?ここでは、主な注意点を3つ解説します。
- 地域振興等機関自身の販路開拓や利益の追求に対して支援する類型ではない
- 要件を満たしても必ず受給できるわけではない
- 補助金は事業実施後の後払いである
地域振興等機関自身の販路開拓や利益の追求に対して支援する類型ではない
1つ目は、地域振興等機関自身の販路開拓や利益の追求に対して支援する類型ではないことです。
共同・協業型で補助対象とされるのは、参画事業者の売上増加などに寄与する取り組みです。地域振興等機関自身の販路開拓や利益追求のための取り組みは、補助対象とはなりません。
要件を満たしても必ず受給できるわけではない
2つ目は、要件を満たして申請をしても、必ず受給できるわけではないことです。
公募期間の満了後、第三者の有識者から構成される委員会によって審査がなされ、採択・不採択が決まります。審査は、最低限の要件を満たしているか否かに加え、次の項目などさまざまな視点からなされることとされています。
- 事業の継続性・持続性の観点から資金調達能力を含め、健全な財務体制となっているか
- 申請者の事業規模や計画に従事する人数、事業実施体制などから、補助事業を計画通りに遂行できる管理・運営能力を有しているか
- 補助事業実施における費用対効果が見合っているか
必ずしも受給できるものではないため、補助金がなければ破綻するような計画を立てないよう注意が必要です。
なお、専門家からコンサルティングを受けて申請内容を練り込むことで事業計画の精度が高まり、採択に近づきやすくなります。お困りの際は、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。
補助金は事業実施後の後払いである
3つ目は、補助金は事業実施後の後払いであることです。
小規模事業者持続化補助金に限らず、補助金の多くは採択がされたからといってその時点で振り込まれるものではありません。採択後はまず自己資金や融資によって調達した資金などを元手として補助対象事業を実施し、実施報告をしてようやく補助金が交付されます。
補助金が受け取れるタイミングについては誤解が少なくないため、全体の流れを理解しておく必要があるでしょう。
小規模事業者持続化補助金の共同協業型の申請の流れ
小規模事業者持続化補助金の共同・協業型への申請は、どのような流れで進めればよいのでしょうか?ここでは、一般的な流れについて解説します。
- 申請サポートを手掛けている専門家に相談する
- 申請内容を練り込む
- 申請する
- 採択・不採択が決まる
- 補助対象事業を実施する
- 実績報告をする
- 補助金が振り込まれる
- 定期報告をする
申請サポートを手掛けている専門家に相談する
小規模事業者持続化補助金の共同・協業型に申請しようとする際は、補助金にくわしい専門家に相談することをおすすめします。専門家へ相談することで、自身が予定している取り組みが補助対象となりそうか否かの判断が可能となるためです。また、専門家にコンサルティングを依頼することで、採択に近づきやすくなるでしょう。
小規模事業者持続化補助金の共同・協業型への申請についてサポートを受ける専門家をお探しの際は、当社トライズコンサルティングまでお気軽にお問い合わせください。
申請内容を練り込む
続いて、専門家とともに申請内容を練り込みます。小規模事業者持続化補助金の共同・協業型では審査の視点が明示されているため、これを踏まえて事業計画の精度をより高めることで、採択の可能性を引き上げることにつながります。
また、専門家からコンサルティングを受けて精度を高めた事業計画は、今後参画事業者の支援を実施する中での拠りどころともなるでしょう。
申請する
申請内容が固まったら、公募期間内に申請します。小規模事業者持続化補助金の共同・協業型はいつでも申請できるのではなく、所定の公募期間内に申請しなければなりません。期限に遅れると申請ができなくなるため、期限管理に注意しましょう。
採択・不採択が決まる
公募期間が満了すると、採択・不採択が決まります。採択がされたら、補助金事務局に対し早急に補助金交付申請を行いましょう。なお、一部の経費区分については、交付申請時に見積書の提出が求められます。
補助対象事業を実施する
補助金事務局から「補助金交付決定通知書」が送付されたら、この時点から補助事業を実施します。交付決定を受けるより前に支出した経費は補助対象から除外されるため、先走らないようご注意ください。
実績報告をする
補助事業を実施したら、実施内容などを取りまとめて実績報告を行います。実績報告では見積書や請求書など一定の証拠書類が必要となるため、紛失したり発行を受けるのを失念したりしないよう、注意が必要です。
補助金が振り込まれる
実績報告に問題がないと判断されると、ようやく補助金が交付されます。補助事業実施のために一時的な借り入れなどをしていた場合には、金融機関との取り決めに従って早期に返済しておきましょう。
定期報告をする
小規模事業者持続化補助金の共同・協業型では、補助金の交付を受けた後も、定期的な報告が必要となります。具体的には、原則として補助事業の完了日の属する会計年度の終了後5年間にわたり、毎会計年度終了後30日以内に「小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>に係る実施効果報告書」を提出しなければなりません。長期間にわたっての報告が必要となるため、報告を忘れないよう注意しましょう。
なお、当社トライズコンサルティングはご要望に応じ、採択後の実績報告や定期報告などのサポートも可能です。サポートをご希望の際は、当社までお気軽にご相談ください。
小規模事業者持続化補助金の共同協業型の最新公募スケジュール
2025年7月現在、小規模事業者持続化補助金の共同・協業型は2025年6月16日(月)に締め切られており、すぐに申請することはできません。
申請をご希望の際は、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。早めからご相談いただくことで公募開始の情報などを見落としづらくなり、申請の機会を逃しづらくなります。
小規模事業者持続化補助金の共同協業型への申請はトライズコンサルティングにお任せください
小規模事業者持続化補助金の共同・協業型への申請は、当社トライズコンサルティングへお任せください。最後に、当社の主な特長を4つ紹介します。
- 小規模事業者持続化補助金の申請サポート実績が豊富にある
- 代表は認定支援機関に登録されている
- 採択後も一貫したサポートが可能である
- 全国対応している
小規模事業者持続化補助金の申請サポート実績が豊富にある
当社トライズコンサルティングは、小規模事業者持続化補助金の申請サポートについて豊富な実績を有しています。地域振興等機関向けの補助金の申請サポート実績も豊富であるため、安心してお任せいただけます。
代表は認定支援機関に登録されている
トライズコンサルティングの代表である野竿は中小企業診断士であるほか、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)としても登録されています。認定支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関です。そのため、確かな知識と実績に裏打ちされた的確なサポートを実現しています。
採択後も一貫したサポートが可能である
先ほど「流れ」でも解説したように、小規模事業者持続化補助金の共同・協業型では、採択後にも実績報告や定期報告などが必要です。これにも相当の手間がかかるものの、これらの手続きまでサポートをする専門家はさほど多くありません。
トライズコンサルティングは、ご要望に応じてこれらの手続きまで一貫したサポートが可能です。
全国対応している
当社トライズコンサルティングはZoomなどのオンラインツールを活用することで、全国対応を実現しています。また、出張先などからも打ち合わせができるため、効率的に申請準備を進めることが可能です。
まとめ
小規模事業者持続化補助金の共同・協業型の概要や補助上限額、申請の流れ、申請時の注意点などを解説しました。
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等が行う販路開拓などの取り組みを支援する補助金です。しかし、この「共同・協業型」はやや特殊な類型であり、小規模事業者等が直接的な補助対象となるのではありません。共同・協業型では、地域の小規模事業者(参画事業者)を支援する地域振興等機関が補助対象とされています。
とはいえ、申請すれば必ず受給できるものではなく、採択される必要があります。審査時に重視されるポイントは公募要領に明記されているため、これを踏まえた事業計画を策定することで採択に近づきやすくなるでしょう。
当社トライズコンサルティングは、小規模事業者持続化補助金の共同・協業型の申請サポートを手掛けています。また、チラシ作成やホームページ制作、マーケティング支援、融資の申込み支援など、総合的な支援も可能です。
共同・協業型への申請をご検討の際や、コンサルティングを受けて申請内容をブラッシュアップしたいとお考えの際は、当社トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。補助金に関する初回のご相談は、無料です。